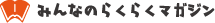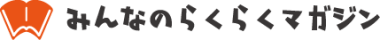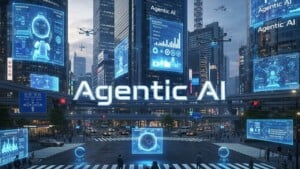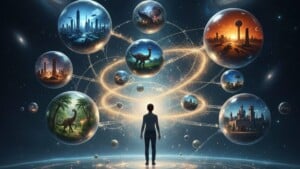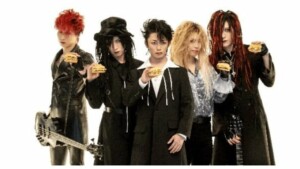2025年9月8日 皆既月食「ブラッドムーン」:赤く染まる月の神秘と歴史、観測ガイド
【この記事にはPRを含む場合があります】

最近、SNSなどで「2025年9月8日に何かが起こる」と話題になっているのをご存知でしょうか。これは、地球、太陽、月が一直線に並び、月が地球の影に隠れて赤く染まって見える「皆既月食」、通称「ブラッドムーン」という天体現象のことです。この神秘的な現象は古くから人類を魅了し、時に不吉な前兆とも考えられてきました。今回は、このブラッドムーンが一体どのような現象なのか、なぜ赤く見えるのか、いつどこで観測できるのか、そしてそれにまつわる都市伝説や歴史上の出来事、次に日本で見られる時期まで、詳しくご紹介していきます。
皆既月食「ブラッドムーン」とは?月の神秘的な変貌

皆既月食、通称「ブラッドムーン」とは、月が地球の影に完全に覆われることで、赤っぽい色に見える天文現象です。この現象は、太陽、地球、月が一直線に並んだときに起こります。通常、月は太陽の光を直接反射して明るく輝いていますが、皆既月食の際には、地球が太陽の光を遮る形となり、月は地球の暗い影である「本影(ほんえい)」の中にすっぽりと入ります。
この状態になると、月は完全に暗くなるのではなく、神秘的な赤銅色に染まって見えます。この深い赤色は、まるで月が血に染まったかのように見えるため、「ブラッドムーン(血の月)」と呼ばれるようになりました。
皆既月食は、太陽が月によって隠される日食とは異なり、特別な道具なしで肉眼で安全に観測できる、数少ない壮大な天体ショーの一つです。また、世界中のどこでも月が見えている場所であれば、同時に観測することができます。
なぜ月は赤く染まるのか?地球大気のフィルター効果

太陽の光が月に直接届かない皆既月食時に、なぜ月が赤く見えるのでしょうか。その理由は、地球の大気による光の散乱と屈折にあります。この現象は、夕日が赤く見える原理と本質的に同じです。
太陽の光は、さまざまな色の光が混ざり合った白色光です。この光が地球の大気を通過する際、波長の短い青い光は大気中の微粒子によって散乱されやすくなります。一方、波長の長い赤い光は散乱されにくく、大気を通り抜ける性質があります。
皆既月食の際、太陽の光の一部は地球の大気圏を通過し、屈折して地球の影の内側にある月までわずかに届きます。この過程で青い成分の光は散乱されて失われ、赤い成分の光だけが月まで到達するため、月は赤く染まって見えるのです。
月の色の濃さや色合いは、その時の地球大気中に含まれるチリ、水蒸気、火山灰などの量によって変化します。大気中の粒子が多い場合は、月は暗い赤色や茶色に見えることがあり、大気が澄んでいる場合は、明るいオレンジ色に見えることもあります。もし月面に立って皆既月食中の地球を見上げると、地球は深い赤色に染まり、その縁にはオレンジ色や赤色の光の環が見えることでしょう。これは、地球上のすべての日の出と日の入りが同時に起こっているかのような、息をのむような光景だと言われています。
2025年9月8日、いつどこで皆既月食が見られる?

2025年9月8日に観測される皆既月食は、日本全国で約3年ぶりに見られる貴重な機会です。この皆既月食は、9月7日の夜に昇った満月が、日付が変わった9月8日の未明から欠け始め、明け方にかけて進行します。
日本での観測時間帯(日本時間)
- 部分食の始まり: 9月8日(月)午前1時27分頃
- 皆既食の始まり: 9月8日(月)午前2時30分頃
- 食の最大: 9月8日(月)午前3時12分頃
- 皆既食の終わり: 9月8日(月)午前3時53分頃
- 部分食の終わり: 9月8日(月)午前4時57分頃
今回の皆既月食は、月が地球の影の中心近くを通るため、皆既食の時間が比較的長く、約1時間22分間にわたって赤く染まった月を楽しめます。部分食の始まりから終わりまでの全行程は約3時間半に及ぶ壮大な天体ショーです。
観測場所と注意点
月食の現象が起こるタイミングは全国共通ですが、その時間帯の月の高度は地域によって異なります。
- 月食は概ね各地で空の高い位置から始まりますが、後半になるほど月が低くなり、地形や建物の影響を受けやすくなります。
- 北日本では月の沈む時刻が早いため、月食を最後まで観測したい場合は、西の空が開けた場所を選ぶと良いでしょう。
- 当日は秋雨前線の影響で、北陸から北日本では雲が多く、観測が難しい可能性があります。東日本や西日本、沖縄では、雲の合間から観測できるチャンスがあるかもしれません。最新の天気予報をこまめに確認することが重要です。
観測方法
皆既月食は肉眼でも十分に楽しめる天文現象であり、特別な道具は必要ありません。しかし、双眼鏡や天体望遠鏡を使うと、月の表面の模様や色の変化をより詳細に、鮮明に観察することができます。カメラで撮影したい場合は、三脚と長時間露光が可能なカメラを用意し、月の明るさの変化に合わせて露出設定を調整すると良いでしょう。
世界での観測状況
この皆既月食は、アジアと西オーストラリアでは全段階を観測できる最高の位置にあります。ヨーロッパ、アフリカ、東オーストラリア、ニュージーランドでも一部の段階が観測可能です。ただし、アメリカ大陸からは観測できません。世界の人口の約77%、およそ62億人がこの皆既月食の全段階を観測できると予測されています。
また、9月8日の夕方には、沈んだ月が再び東の空から昇ってきた際、そのすぐそばに明るい土星が見える接近現象も起こります。月食と直接は関係ありませんが、これもまた楽しめる天体現象の一つです。
「ブラッドムーン」にまつわる都市伝説と歴史的記録

「ブラッドムーン」という言葉は、古くから不吉な出来事の前兆として語り継がれてきました。これは単なる都市伝説の域を超え、聖書や古代の伝承にもその記述が見られ、歴史上の重要な出来事と奇妙な一致を見せることもあります。
聖書に記された予言
旧約聖書の「ヨエル書」には、「主の恐るべき大いなる日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる」という予言が記されています。また、新約聖書の「ヨハネの黙示録」には、「第六の封印が解かれたとき、太陽は粗布のように黒くなり、満月は血のように赤くなった」という記述もあります。これらの言葉は、長い歴史の中で「赤い月=不吉な出来事の前兆」というイメージを世界中に広めてきました。
古代の信仰と伝承
古代バビロニアでは、月食を「悪魔が月を食べている現象」と捉え、太鼓を叩いて大きな音を出すことで悪魔を追い払おうとしたと言われています。中国では「天の犬が月を食べる」と信じられ、鍋や皿を叩いて犬を驚かせる習慣がありました。インカ帝国では、ジャガーが月を攻撃していると考えられていました。また、「ルナティック(lunatic)」という言葉は、月(Luna)に由来し、月の満ち欠けが人間の精神状態に影響を与えるという古い信仰を反映しています。
歴史上の「ブラッドムーン」と出来事
科学的には明確な因果関係は証明されていませんが、歴史を紐解くと、ブラッドムーンの後に大きな変動や不吉な出来事が続いた記録が多数残されています。
- 1492年
クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸に到達したこの年、スペインではユダヤ人追放令が出され、中世最大の反ユダヤ運動が広がりました。この時期、ヨーロッパ各地で皆既月食が観測されていたという記録があります。 - 17世紀の三十年戦争
ヨーロッパで頻繁に皆既月食が観測されていた時期です。当時の人々は赤い月が戦争を呼ぶと恐れていました。この戦争でドイツの人口は1600万人から約1000万人へと、約3分の1が失われるほどの惨事となりました。 - 14世紀の黒死病大流行
この時期の夜空には赤い月が浮かんでいたという記録が残されています。 - 2018年1月31日のスーパーブラッドムーン
スーパームーン、ブルームーン、皆既月食が同時に起こる非常に珍しい現象でした。その翌年、2019年には中国武漢で新型コロナウイルスが確認され、世界的なパンデミックへと発展。現代が経験したことのない大混乱の時代に突入しました。 - 1866年3月31日のスーパーブラッドムーン
日本ではこの年に徳川慶喜が第15代将軍に就任し、明治維新へと続く重要な変化が始まりました。 - 「テトラッド」(4回連続皆既月食)
- 1949年: イスラエル建国直後の第一次中東戦争と時期が重なりました。
- 1967年〜1968年: 第六次中東戦争(六日戦争)とエルサレム旧市街奪還の時期と一致しています。
- 2014年〜2015年: イスラエルとガザ地区の紛争が起こった時期と重なっています。
これらの事例は単なる偶然として片付けられることもありますが、赤い月の後に時代が大きく変わったという見方をする人も少なくありません。満月の日に犯罪率が高いという統計も存在しますが、これは科学的な根拠が確立されているわけではありません。それでも、ブラッドムーンという天体現象が人々の想像力を刺激し、大きな出来事との関連性が語り継がれてきたのは事実です。
日本で次に皆既月食が見られるのはいつ?

2025年9月8日の皆既月食を見逃してしまっても、次に日本で皆既月食が観測できる機会は、2026年3月3日です。
この2026年3月3日の皆既月食は、深夜から未明にかけての観測となる2025年9月8日とは異なり、夕方から夜にかけて見られるため、多くの人にとってより観測しやすい時間帯となるでしょう。食の最大時間は20時34分頃と予測されています。
皆既月食は、地球上のどこかでは年に数回発生することもありますが、同一地点から観測できる頻度は平均して約2年半に1回程度とされています。今回の皆既月食は82分間という比較的長い時間、皆既食を楽しむことができる貴重なチャンスです。次にこれほど良い条件で日本から見られるのがいつになるかは分かっていません。
皆既月食の発生周期には、約18年11日という「サロス周期」と呼ばれるものがあり、この周期によって似たような条件の月食が繰り返し発生することが知られています。古代バビロニア人もこの周期を発見し、月食の予測に活用していました。
宇宙の神秘と私たちの備え:ブラッドムーンを迎える前に

2025年9月8日に訪れる皆既月食、通称「ブラッドムーン」は、宇宙が織りなす壮大な天体ショーです。赤銅色に染まる月は、見る人に深い感動と神秘的な感覚を与えてくれることでしょう。このような皆既月食は、いつでも見られるものではありません。深夜から明け方にかけての現象ではありますが、もし時間と機会があれば、ぜひ夜空を見上げて、この貴重な天文現象を体験してみてください。
ブラッドムーンにまつわる都市伝説や、歴史上の大きな出来事との奇妙な一致は確かに存在します。古くから人々は、赤い月に不吉な前兆を見出し、恐れてきました。しかし、現代の科学的な見地からすれば、皆既月食は地球と太陽、月の位置関係によって起こるごく自然な現象であり、そのものに特定の「災い」をもたらすという根拠はありません。
過度に不安を抱いたり、心配しすぎたりすることなく、純粋に天体現象としての美しさを楽しむことが大切です。宇宙の広大さや地球の営みに思いを馳せる良い機会として、このブラッドムーンを迎えるのはいかがでしょうか。科学的な知識を持ってこの現象を理解し、その上で悠久の宇宙の神秘に触れることは、私たちにとって貴重な体験となるはずです。
この機会に、家族や友人と一緒に夜空を見上げ、共通の記憶と思い出を共有するのも素晴らしいでしょう。スマートフォンや双眼鏡、望遠鏡を使って、普段とは違う月の表情を観察してみてください。
備えあれば憂いなしという言葉があるように、日常生活でできる防災対策を見直す良い機会と捉えることもできます。避難経路の確認、連絡手段の把握、防災用品の備蓄など、日ごろからの備えはどんな状況においても重要です。
私たちは今、地球の大きな変動期に入っているとも言われますが、大切なのは、科学的根拠に基づいた情報を知り、冷静に判断することです。ブラッドムーンをきっかけに、宇宙や自然現象への関心を深め、未来に向けて賢く行動するきっかけにしていただければ幸いです。
みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)
SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。