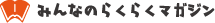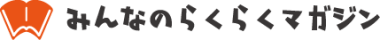【緊急警報】クレジットカード規制強化で日本コンテンツが危機に?深まる検閲の実態と表現の自由への影響
JCB / Mastercard / Visa
【この記事にはPRを含む場合があります】

近年、世界中でクレジットカード決済に関する規制が強化され、特に日本のデジタルコンテンツ業界に大きな波紋を広げています。漫画、アニメ、ゲームといった幅広いジャンルのコンテンツが影響を受け、その背後には、海外の決済企業の倫理基準や圧力団体の活動が見え隠れします。この規制強化は、単なるビジネス上の問題に留まらず、表現の自由や文化の多様性にも深刻な影響を与える可能性が指摘されており、国際的な議論を巻き起こしています。
クレジットカード決済規制強化とは?なぜ日本コンテンツが標的に?
クレジットカード決済規制強化とは、国際的なクレジットカードブランドや関連企業が、自社の規約に基づき、特定のコンテンツやサービスの決済を制限する動きを指します。これにより、これまで販売されていた合法的なコンテンツであっても、クレジットカード決済ができなくなるケースが相次いでいます。
この問題が特に日本コンテンツに影響を与えるのは、海外のクレジットカード会社が、日本とは異なる倫理基準やコンプライアンスを適用し始めているためです。彼らは「違法またはブランド価値を損なう取引」を禁止する規約を理由に、アダルトコンテンツの取り扱いを制限しています。さらに、明確な基準が示されないまま規制が進むため、合法的なコンテンツまでもが影響を受けている状況です。
この動きの背景には、オーストラリアを拠点とする圧力団体「Collective Shout(コレクティブシャウト)」のような活動が挙げられます。彼らは、メディアやポップカルチャーにおける女性の客観視や少女の性的表現に反対する草の根キャンペーンを展開し、ゲームプラットフォーム上の大人向けコンテンツに対する規制を求めています。当初、Steamのようなプラットフォームに直接働きかけましたが、応答がなかったため、PayPal、Mastercard、Visa、Discoverといった主要な決済処理業者に直接圧力をかける戦略に転換しました。
VISAとMastercardに集中する批判の声
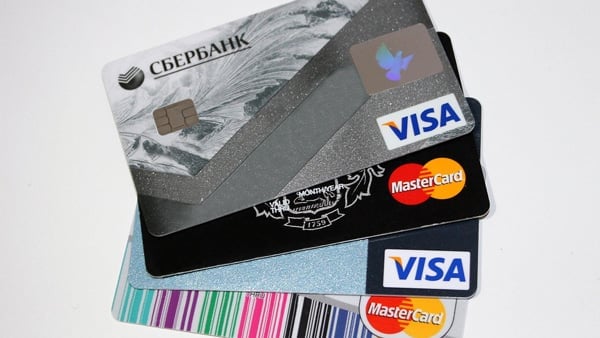
クレジットカード決済の仕組みは、ユーザー、ストア(加盟店)、国際ブランドの3者だけでなく、カードを発行するイシュア、加盟店を管理するアクワイアラ、そしてそれらをまとめる決済代行業者など、複数の関係者が関与する多層的な構造をしています。
この複雑な構造の中で、国際ブランドであるVisaやMastercardは、自社のブランド価値を損なう可能性のあるコンテンツに対して、決済サービスを利用させないという方針を間接的に示しています。例えば、Mastercardの規約には「違法またはブランド価値を損なう取引を禁止し、明らかに不快で芸術的価値を欠く製品またはサービスの販売を制限する」という条項が存在します。
しかし、国際ブランドが直接「このコンテンツはダメ」と指示するのではなく、その傘下にあるアクワイアラや決済代行会社が、国際ブランドの顔色をうかがい、より厳しめに規約を解釈して加盟店にNGを出す「忖度」が横行していると考えられています。これが、「なぜこのコンテンツまで?」という疑問を生み、混乱を招く原因となっています。
実際に、Visaは過去に日本を含むアジア太平洋地域で、自社の決済ネットワークを使用しない場合に手数料の優遇を適用しなかったとして、独占禁止法違反の疑いで行政処分を受けています。これは、決済の分野における大手カード会社の強大な影響力を示す事例と言えるでしょう.
規制のきっかけと歴史的背景
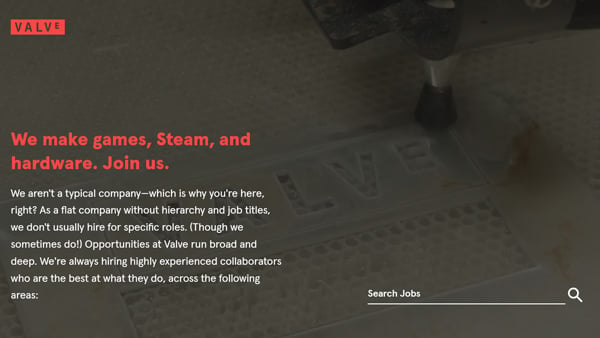
(出典:Valve)
クレジットカード決済の規制強化は、約2019年頃からその傾向が見られ始め、2024年に一気に広まりました。当初は、海賊版コンテンツのような「違法な」アダルトサイトが主な規制対象でしたが、徐々にその線引きが曖昧になり、合法的なコンテンツにまで影響が及び始めたのです。
具体的なきっかけとしては、2022年7月にDMM.comでMastercardの利用が停止されたことが挙げられます。これを皮切りに、電子書籍配信サイトの漫画図書館Zや同人誌通販のメロンブックスなど、日本の様々なコンテンツサービスでクレジットカード決済の利用停止が相次ぎました。これらのサービスは、決済代行会社からアダルトコンテンツの取り扱いを理由に契約解除を通達されたと説明しています。
コレクティブシャウトは、2025年7月10日にPayPal、Mastercard、Visaといった決済業者に対し、Steam上の「性的な虐待ゲームで利益を得ている」と主張し、決済処理を停止するよう求める公開書簡を送付しました。その結果、Steamを運営するValve社は、決済処理業者やカードネットワーク、銀行、インターネットプロバイダーが定める基準に違反する可能性のあるコンテンツの配信を制限する新たなガイドラインを公開せざるを得なくなりました。
この動きは、過去に海外でクレジットカード会社が違法コンテンツへの資金流通に関与したとして訴訟に巻き込まれた経験があり、同様のリスクを避けるために予防的な措置を講じている側面もあると考えられています。カード会社は「違法か健全か」の区別をする手間を避けるため、全てを禁止する方が楽だと判断しているとの指摘もあります。
どのようなコンテンツが規制対象になっているのか

(出典:PR TIMES)
当初、クレジットカード決済の規制は、自動ポルノのような明確に違法なコンテンツに限定されていました。しかし、現在では「明らかに不快で芸術的価値を欠く製品」という曖昧な基準が適用され、その解釈は広範にわたっています。
具体的には、Steamで削除されたゲームには、性的な暴力や虐待をテーマにした作品が含まれているとされています。また、コレクティブシャウトは、性的な表現を含む日本のゲームやアニメ(例:ソードアート・オンライン、ゴブリンスレイヤー)についても規制を求めています。
この規制の曖昧さは、「オタク婚活サービス」のような一見無関係なサービスまでもが影響を受ける事例を生み出しました。さらに、「少しの肌の露出」や「肌の色」さえも問題視される可能性が懸念されるなど、過剰な解釈が進む危険性も指摘されています。
LGBTQ+をテーマにしたゲームも、NSFW(Not-Safe-For-Work)コンテンツとして検索結果から一時的に非表示にされるなど、意図しない形で影響を受けるケースも発生しています。
現在の状況と講じられている対策

クレジットカード決済の規制強化は、現在もゲーム業界全体に大きな影響を与え続けています。
Steamの対応
Steamは、決済処理業者や銀行の規約に違反する可能性のあるコンテンツの配信を制限するガイドラインを更新し、結果として数百ものゲームが削除される事態となりました。Steamは、顧客への支払い方法の提供を維持するためには、これらのゲームの販売を終了せざるを得なかったと説明しています。
ゲーマーコミュニティの反発
この状況に対し、ゲーマーコミュニティからは強い反発が起こり、Change.orgでは18万人以上の署名が集まるなど、反対運動が続いています。イーロン・マスク氏も、この動きを批判する姿勢を示しています。
圧力団体の動き
コレクティブシャウトは、ゲーマーからの批判やハラスメントを受けていると主張し、警察に報告する準備を進めているとされています。また、X(旧Twitter)での大人向けコンテンツ規制も積極的に求めています。
政府レベルの動き
オーストラリアやイギリスでは、政府レベルでの年齢認証導入の動きとも連携していると見られており、厳格な方法が検討されています。日本では、経済産業省や金融庁がこの問題に関して協議を行っています。
表現の自由への懸念
この問題は、「ポリコレ(ポリティカル・コレクトネス)」の影響と類似する点が多く、コンテンツの創造性や多様性が過度な規制によって損なわれることへの懸念が高まっています。例えば、カナダのコンサルティング会社Sweet Baby Inc.が推進する「DEI(多様性・公平性・包括性)」の考え方が、ゲームの世界観を損なう「過度なポリコレ化」として批判を集めるケースもあります。
こうした状況に対し、一部からは、日本も独自の決済システムを構築し、外部からの不当な影響を排除すべきだという意見も出ています。
JCBと他のカード会社の動向

(出典:PR TIMES)
VisaやMastercardといった海外大手ブランドが規制を強化する中、JCBは比較的、日本のコンテンツに対して寛容な姿勢を保ってきました。多くのユーザーは、VisaやMastercardが利用できなくなったサイトで、JCBカードであれば決済が可能であると認識していました。
しかし、コレクティブシャウトは、VisaやMastercardだけでなく、PayPalやJCBに対しても、Steamや類似のゲームプラットフォームでの決済処理を直ちに停止するよう求める公開書簡を送付しており、日本企業であるJCBも標的にされていることが明らかになっています。
これは、海外の倫理基準や宗教的な思想(特にキリスト教系の保守的な思想)が、日本の文化や表現の自由に直接的に影響を及ぼし始めていることを意味します。日本はキリスト教国家ではないため、なぜ日本の基準が海外のグローバル基準に合わせなければならないのか、という批判の声も上がっています。
創作と文化の未来を守るために
クレジットカード決済の規制強化は、単なる決済手段の問題に留まらず、私たちの表現の自由と文化的な多様性に対する挑戦です。国際的なカード会社が、自らの倫理基準やブランドイメージに基づいて、コンテンツの流通を実質的に「検閲」し、その是非を判断する権限を握っている状況は、極めて問題であると言えるでしょう。
この規制が過度に進めば、ゲーム、漫画、アニメ、イラスト、映画、同人誌といったあらゆる種類の創作物に波及する可能性があり、日本の創造的な文化全体が標的にされる懸念があります。もし合法的なコンテンツまでもが販売できなくなれば、クリエイターの生計が脅かされるだけでなく、消費者が多様なコンテンツに触れる機会も失われます。
また、合法的な消費の場が失われることで、かえってアングラな市場が拡大し、取り締まりが困難になるなど、結果的に社会にとって望ましくない状況を生み出す可能性も指摘されています。
私たちは、企業が社会のコンプライアンスや倫理基準を遵守することの重要性を理解しつつも、それが表現の自由や文化の多様性を不当に侵害することのないよう、強い懸念を表明すべきです。政府や関連機関は、日本の法的・文化的基準に基づいた決済インフラの構築や、国際的な議論への積極的な介入を通じて、アーティストの創造活動と消費者の選択の自由を守るための対策を講じる必要があります。
みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)
SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。