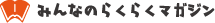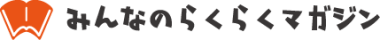【安全対策ガイド】 リチウムイオン電池の危険性と正しい扱い方|安全な購入・処分で事故を防ぐ
【この記事にはPRを含む場合があります】
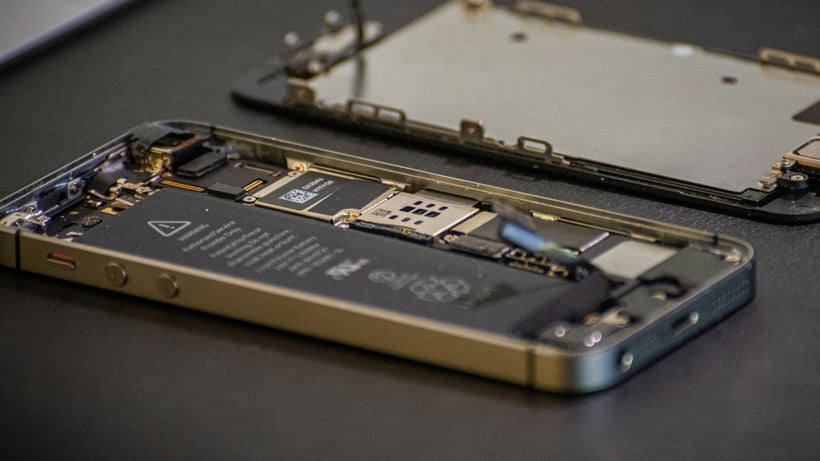
私たちの生活に欠かせない存在となったスマートフォンやノートパソコン、電動工具など、多くの電子機器に搭載されているリチウムイオン電池。そのコンパクトさや高性能さから、今やなくてはならないものですが、その一方で、取り扱いを誤ると発火などの重大な事故につながる危険性も秘めています。便利さの裏に潜むリスクを正しく理解し、安全に使いこなすことが重要です。
リチウムイオン電池とは?その普及と特性
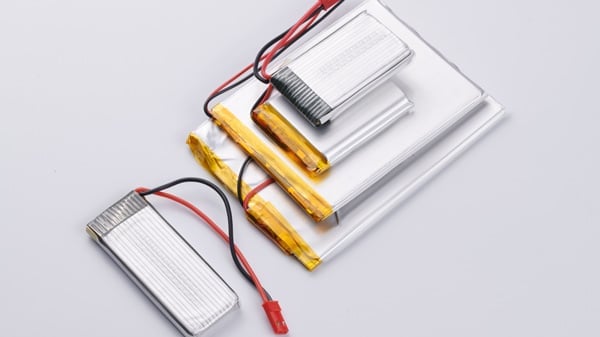
リチウムイオン電池は、充電して繰り返し使える二次電池の一種です。特に、高い起電力、大電流を流せる能力、そして高いエネルギー密度が特徴で、軽量で比較的長寿命であるため、幅広い用途で利用されています。
リチウムイオン電池の内部は、主に正極、負極、電解質、セパレーターで構成されています。
正極と負極
それぞれ異なる材料が使用されており、例えば正極材はアルミニウム箔に、負極材は銅箔にコーティングされています。これらの電極は、イオンを貯蔵する「貯蔵庫」の役割を果たします。
電解質
正極と負極の間に位置し、電気を流す導電性は持たず、イオンのみを通す性質を持っています。これにより、リチウムイオンだけが効率的に電極間を移動できます。
セパレーター
電解質と同様に導電性がなく、正極材と負極材が物理的に接触して短絡するのを防ぐ障壁として機能します。無数の小さな穴が空いた多孔質構造のため、リチウムイオンは通過できます。
集電体
電極間を移動する電子を受け取り、外部回路へ伝える重要な役割を担っています。
充電時には、バッテリーに電圧がかけられると、正極から電子が引き離され負極へ移動します。この電子は電解質を通過できないため、集電体から外部回路を通って負極へと流れます。電子を失ったリチウム原子は正の電荷を持つリチウムイオンとなり、電解質を介して電子が移動した負極へと追従します。これにより、無数の電子とリチウムイオンが負極に蓄積され、バッテリーが充電されます。負極材料にはグラファイト(黒鉛)が広く使われ、リチウムイオンはグラファイトのカーボン層の隙間に挿入されます。
放電時には、電子機器が接続されると、負極に貯蔵されていたリチウムイオンと電子は正極に移動します。リチウムイオンは電解質を通って正極へ向かい、電子は外部回路を通って正極へ移動します。この独立した電子の流れが電流を生み出し、接続された電子機器に電力を供給します。
電子とイオンが別々の経路で移動する仕組みは、内部短絡を防ぐだけでなく、電気エネルギーを効率的に取り出すためにも重要です。
身近に潜む?リチウムイオン電池が使われる製品

リチウムイオン電池は、その優れた性能から私たちの身の回りにある非常に多くの製品に搭載されています。主な用途は以下の通りです。
- モバイル機器:スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど、充電して持ち運ぶほとんどの電子機器。
- 家庭用電化製品:モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電子タバコ、携帯扇風機、コードレス掃除機など。
- 電動モビリティ:電気自動車、ハイブリッド車、電動二輪車、電動アシスト自転車など。
- 産業機器:建設機械、農業機械、産業機械、蓄電システムなど、大型の装置やシステム。
- その他:フラッシュライトや、自作の電子工作の電源などにも利用されます。
これらの製品の普及に伴い、リチウムイオン電池の適切な取り扱いと廃棄がますます重要になっています。
知っておきたいリチウムイオン電池の危険性と発火の仕組み

リチウムイオン電池は便利である反面、誤った使用や廃棄方法によって、発煙・発火の危険性があります。
発火が起こる主な仕組み
劣化とガス発生
リチウムイオン電池は使用を続けると劣化し、内部にガスが溜まって膨張することがあります。このガスは可燃性であるため、さらに温度が上昇したり、内部で短絡したりすると引火する可能性があります。
過充電・過放電
バッテリーの電圧が推奨範囲(例:満充電4.2V~放電2.7V)を超えて充電される「過充電」や、電圧が下がりすぎる「過放電」は、バッテリーに大きなダメージを与えます。特に過充電は、バッテリー内部で化学反応が促進され、急激な温度上昇、ガス発生、膨張、さらには破裂や発火につながる可能性があります。
物理的損傷
リチウムイオン電池は衝撃や外部からの圧力、高温に非常に弱いです。強い力で潰されたり、傷つけられたりすると、内部で短絡(ショート)が発生し、発熱・発火を引き起こすことがあります。
近年、リチウムイオン電池が原因とみられる火災事故が多発しており、ゴミ収集車やゴミ処理施設での火災が特に問題となっています。国立研究開発法人製品評価技術基盤機構(NITE)によると、2018年度からの4年間で、リチウムイオンバッテリーの発火などによる被害額は約111億円に達し、年々増加傾向にあります。環境省の調査では、リチウムイオン電池が原因の火災は年間1万件以上に上り、これは毎日複数の場所で事故が起きている計算になります。
リチウムイオン電池の正しい購入と保管方法
リチウムイオン電池はデリケートな製品であり、購入時や保管時にも注意が必要です。
購入時の注意点
信頼できるメーカー・販売店を選ぶ
非正規の販売品や、異常に安価な製品は、品質が保証されず、トラブルの原因となる可能性があります。特に、自分でバッテリーパックを組んだり、デバイスに組み込んだりするために「セル」と呼ばれる単体電池を購入する際は、高性能で品質の高いメーカーの「A品」セルを選ぶことが推奨されます。A品セルは、メーカーで厳密に検査され、バラつきがなく均質な「優良品」であり、生産ロット番号も揃っています。一方、「B品」セルは、検査で弾かれたバラつきのあるものが集められたもので、品質が劣るため、バランスが崩れやすく、すぐに使えなくなることがあります。
保護回路付きを選ぶ
モバイルバッテリーなど、完成品として販売されているリチウムイオン電池製品には、通常、過充電や過放電、過電流、過熱などを防ぐ保護回路が搭載されています。この保護回路が、電池を安全に使うための重要な役割を果たします。
保管方法
適切な温度で保管する
リチウムイオン電池は極端な高温や低温に弱いです。一般的なリチウムイオン電池の動作温度範囲は0℃から35℃とされており、保管時もこの範囲に近づけることが望ましいです。特に夏場の車内など、高温になる場所での保管は避けてください。
膨張などの異常がないか確認する
使用を続けるうちにバッテリーが膨張することがあります。これは内部でガスが発生しているサインであり、劣化の兆候です。膨張したバッテリーはすぐに使用を中止し、発火の危険性があるため、可燃物のない場所に移すなどの対策が必要です。例えば、一時的に金属製の缶に入れてベランダなど安全な場所に移動させる方法が提案されています。
衝撃や圧力を避ける
保管中に落下させたり、重いものを乗せたりして強い衝撃や圧力が加わると、内部が損傷し、発火につながる可能性があります。
正しい処分方法で事故を防ぐ!リチウムイオン電池の廃棄
リチウムイオン電池は、一般ごみとして安易に捨ててはいけません。不適切な廃棄は、ゴミ収集車やゴミ処理施設での火災事故に直結する非常に危険な行為です。
正しい廃棄方法のポイント
- 自治体のルールを確認する:リチウムイオン電池の処分方法は、各自治体によって異なります。粗大ごみ、不燃ごみ、回収ボックスなど、ウェブサイトや分別カレンダーで必ず確認し、地域のルールに従ってください。
- 回収協力店を利用する:多くの家電量販店やホームセンターには、リチウムイオン電池の回収ボックスが設置されています。また、一部のメーカーや販売店でも回収サービスを提供している場合があります。
- JBRCによる回収・リサイクル:一般社団法人JBRCは、資源有効利用促進法に基づき、小型充電式電池(リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池)の回収・リサイクルを行っている団体です。回収協力店はJBRCのウェブサイトで確認できます。
- 必ず放電してから廃棄する:バッテリーに電気が残っている状態で廃棄すると、衝撃などで発火する危険性があります。廃棄する前には、電気エネルギーをなくす(放電させる)必要があります。
- 分解が難しい場合は無理をしない:製品にリチウムイオン電池が内蔵されていて、自分で取り外すのが難しい場合、無理に分解しようとするとかえって危険です。その場合は、バッテリーを外さずに、自治体が定める「特定ご品目」などの回収区分に従って廃棄するようにしてください。
特に膨張してしまったバッテリーは回収を断られるケースが多く、処分方法が見つからずに困ることもあります。このような場合でも、絶対に一般ごみとして捨てず、自治体や専門機関に相談することが重要です。
次世代電池の選択肢「ナトリウムイオン電池」の可能性

(出典:PR TIMES)
リチウムイオン電池が抱える資源の偏在やコスト、安全性といった課題を解決する次世代の電池として、ナトリウムイオン電池が注目されています。特に、エレコムが世界で初めてナトリウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリーを発売したことで、モバイルバッテリーの新たな安全性の基準を打ち立て、この次世代電池への期待がさらに高まっています。中国のCATLなど世界的な電池メーカーが2025年中の量産開始を発表しているほか、米国ではナトロン・エナジーが2024年4月末に商業規模での生産を開始し、米国初の事例となりました。
ナトリウムイオン電池の主な特徴
豊富な資源量
ナトリウムは、海水中に大量に含まれるなど、リチウムに比べて非常に豊富に存在します。地球上の資源量はリチウムの約1,200倍とも言われ、特定の地域に偏ることなく、世界中で入手可能です。このため、地政学的なリスクが低く、将来的なコスト安定性も期待されています。
高い安全性
ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池に比べて本質的に安全性が高いと言われています。
- 自己発熱温度が高い:電池内部の化学反応による自己発熱が始まる温度が、ナトリウムイオン電池の方がリチウムイオン電池よりも高いため、熱的に安定しています。
- デンドライト形成のリスク低減:リチウムイオン電池で問題となる、金属リチウムの樹枝状結晶(デンドライト)がセパレーターを突き破り短絡するリスクが、ナトリウムは金属が柔らかいため低いと考えられています。
- 広い動作温度範囲:例えば、市販のナトリウムイオン電池搭載モバイルバッテリーは、リチウムイオン電池の0℃~35℃に対し、-35℃から50℃という非常に広い温度範囲で動作可能です。これにより、雪山や砂漠のような過酷な環境でも利用できる汎用性があります。
長寿命
リチウムイオン電池が500〜800回の充電サイクル寿命とされるのに対し、ナトリウムイオン電池は5000回もの充放電が可能な製品も登場しており、非常に長期間の使用が期待できます。
課題と今後の展望
現在のナトリウムイオン電池には、リチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が低いという課題があります。例えば、東北大学などの研究チームが3Dプリンターで開発した「ジャングルジム構造」の炭素材料を負極に用いることで、電極面積あたりの容量を4倍に高めることに成功しましたが、体積あたりの容量では既存のリチウムイオン電池の3分の1から4分の1程度にとどまっています。これは電極に穴を開けてイオンの通り道を作った結果、貯蔵スペースが減るためです。研究チームは、3Dプリンターの解像度向上により、貯蔵庫の柱を細かく増やし、穴の大きさを最小限にすることで容量を増やすことを目指しています。
また、現状では寿命の短さ(試験結果で100回充放電後に20%容量低下)や、生産コストの高さも課題として挙げられます。しかし、中国のCATLのような世界的な電池メーカーが2025年中の量産開始を発表するなど、技術開発は急速に進んでいます。将来的には、エネルギー密度の向上とコスト削減が進むことで、より小型・軽量で安全なナトリウムイオン電池が普及し、リチウムイオン電池の課題を補完する存在となることが期待されています。
リチウムイオン電池との賢い付き合い方:安全な未来のために
リチウムイオン電池は、私たちの暮らしを豊かにする上で欠かせない技術ですが、その利便性と引き換えに、取り扱いを誤ると重大な危険を伴うことを忘れてはなりません。
まず何よりも、リチウムイオン電池が内蔵された製品を、安易に一般ごみとして捨てないことが重要です。ゴミ処理施設での火災が多発している現状を踏まえ、一つ一つの製品が潜在的な火災の原因となり得ることを認識し、私たち一人ひとりが責任ある行動を取る必要があります。
そのためには、お住まいの自治体が定めるリチウムイオン電池の正しい処分方法を必ず確認し、それに従って廃棄するようにしてください。家電量販店やメーカーの回収サービス、JBRCなどの専門機関の利用も積極的に検討しましょう。膨張などの異常が見られるバッテリーは特に危険なため、専門機関に相談するなど、より慎重な対応が求められます。
また、製品の購入時には、信頼できるメーカーの、保護回路が内蔵された正規の製品を選ぶことも大切です。バッテリーの劣化は避けられないため、長期間使用したモバイルバッテリーなどは、定期的な買い替えや点検を心がけることも、事故を防ぐ上で有効です。
そして、現在課題を抱えるリチウムイオン電池の未来を拓く存在として、ナトリウムイオン電池をはじめとする次世代電池の技術革新に大いに期待が寄せられています。エネルギー密度や寿命などの課題を克服し、より安全で持続可能な電池が実用化されることで、私たちの暮らしはさらに豊かで安心なものになるでしょう。日々の生活の中でリチウムイオン電池と賢く付き合い、安全な未来を共に築いていきましょう。
みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)
SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。