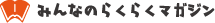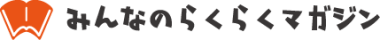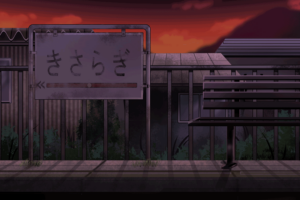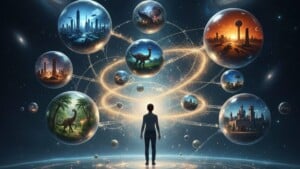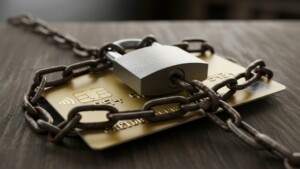中国「ネズミ人間」の絶望と抵抗:横たわる若者たちが社会に突きつける構造的な問題
【この記事にはPRを含む場合があります】

近年、中国社会の光の当たらない場所から、ある新しい社会現象がバイラルな用語と共に急速に広がり、注目を集めています。それが「ネズミ人間(Rat People)」です。
この現象は、かつて話題になった「寝そべり族(Lying Flat)」のトレンドをさらに超えたものとして捉えられており、中国の若者たちが抱える深刻な絶望や社会への静かな抵抗の象徴として、その動画投稿は瞬く間に中国国内のプラットフォームで数億回以上の視聴を集めています。
なぜ今、若者たちは自らをネズミ人間と呼び、低エネルギーで消極的な生活を選ぶのでしょうか。この記事では、ネズミ人間たちの実態、彼らが生まれた背景にある中国社会の構造的な問題、そして、すでに世界や日本でも起きている類似現象との関連性について詳しく紹介していきます。
SNSで話題沸騰!「ネズミ人間(Rat People)」の正体に迫る

ネズミ人間(中国語でラオシューレン)とは、文字通り「ネズミのような人々」を意味する言葉です。この用語が指すのは、主に二つの側面があります。一つは物理的な意味合いで、もう一つは比喩的な意味合いです。
物理的な意味でのネズミ人間(鼠族)については後述しますが、現在SNSなどでバイラルになっているネズミ人間は、主に比喩的な意味で使われています。彼らは、都市の一角でネズミのように生きる人々を指し、高いプレッシャーに直面し、臆病で用心深く、不規則なスケジュールで夜間に活動するという特徴を持っています。
彼らのライフスタイルは「低エネルギー」であることが最大の特徴です。多くはベッドに横たわり、ひたすらスマートフォンをスクロールして過ごします。不安を感じてはいるものの、完全に諦めることはせず、静かに苦境に耐え忍ぶ姿が見られます。まるで「割れ目の中で生き残っている小さなネズミ」のように感じているため、自嘲的に自らをネズミ人間と呼んでいるのです。
この低エネルギーな生活様式に関するトピックは、中国のプラットフォームで1億回以上の視聴を集めており、ネズミ人間に関するトピックに至っては20億回近くの閲覧数を誇るほど、今年の最も注目される新しいペルソナとなっています。
ネズミ人間たちの「低エネルギー」な日常と行動様式

ネズミ人間たちの日常は、従来の「成功」を追い求める生活とはかけ離れたものです。
昼夜逆転と引きこもり生活
ネズミ人間とされる若者の一日は、昼過ぎ、あるいは正午ごろにようやく目覚めるところから始まります。起床してもすぐにまたベッドに戻り、日中の大半をベッドの上で過ごします。ベッドは彼らにとって、司令塔であり、同時に監獄でもあるのです。彼らの生活の中心はデジタル空間に完全に移行しており、現実の人間関係はほぼ途絶えています。
彼らの主な活動は、スマホをスクロールしたり、ファンタジー番組を一気見したりして、心の中の虚無感を麻痺させることです。エネルギーを節約するため、会話の際に大声を出したがらない者さえいます。外出の基準は部屋にゴミが溜まったかどうかという女性もおり、何もなければ一日中カーテンも開けずに部屋にこもるのが日常です。中には、シャワーを浴びることがオプションになっている者や、深夜2時にシャワーを浴びる者もいます。
究極のミニマリストな食生活と欲望の拒絶
ネズミ人間たちの食生活は、驚くほどミニマリストです。彼らの食事は主にデリバリーアプリで注文され、ベッドの上で済ませてしまうこともあります。中には、一ヶ月の出費を300円未満(40米ドル未満)に抑え、一日にサンドイッチ一つ、インスタントラーメン、水道水だけで生きる者もいます。
これは単なる節約やダイエットではなく、欲望そのものの拒絶なのです。成功の基準が中身のない指標で測られ、休息さえも生産的でなければならない社会に対して、彼らは立ち止まり、競争という「ハムスターの回し車」から降りることを選択しています。
ネズミ人間を生み出した中国社会の構造的な闇

このネズミ人間現象は、中国がかつて約束した「繁栄の夢」が、数百万人の若者にとっては裏切りとなった現実を物語っています。
過酷な労働環境と報われない努力
ネズミ人間が生まれた背景には、中国の経済成長モデルの限界と、若者を消耗させる競争社会があります。中国では「996」(朝9時から夜9時まで週6日働くサイクル)と呼ばれる過酷な労働環境が蔓延しており、これは過労死ライン(月80時間以上の残業)を遥かに超えるレベルです。
若者たちは、一生懸命働いても、高騰し続ける家賃と生活費、そして将来の経済的な安定が手に入らないことに直面しています。彼らは、勝てないと知っているゲーム(競争)に参加することを拒否しています。
若年層の深刻な失業と教育のミスマッチ
中国は毎年3000万人以上の大卒者を輩出していますが、これほどの教育を受けた労働力が余剰となり、実際の仕事が不足しているという厳しい現実に直面しています。2025年には大学卒業生が過去最多の1220万人となり、16歳から24歳の若年層の失業率は15%以上、一部では18.9%にまで上昇するという高水準が続いています。
企業は採用を控える一方、大学で学んだ金融やITの知識と、実際に求人が多い物流や小売などの現場労働者との間に大きなミスマッチが生じています。この結果、「ネイジュア」(内巻、無意味で過剰な競争)と呼ばれる現象が深刻化し、努力の量が増えても成果が伴わない状況が、若者の無力感を募らせています。
経済の停滞と信頼の崩壊
米中貿易戦争による輸出関税の上昇、国内需要の飽和、消費支出の急落などが、経済の減速を引き起こしています。かつて「メイド・イン・チャイナ」の屋台骨だった製造業でも、工場が閉鎖し、大規模な失業が伝染病のように広がっています。
不動産市場の崩壊などにより、人々は資産に対する信頼を失い、消費を控えるという悪循環(デフレ・スパイラル)に陥っています。このような社会の状況下で、若者たちは将来への希望や、社会に対する信仰をすべて失い、「生きる屍」のように静かに横たわることを選んでいるのです。
「寝そべり族(唐平)」との決定的な違いと進化

ネズミ人間は、数年前に話題となった「寝そべり族(タンピンズ)」の動きを継承しつつも、より深刻な段階へと進化した現象だと指摘されています。
寝そべり族(Lying Flat / 唐平)
寝そべり族は、終わりのない過酷な競争から意図的に離脱することを選んだ若者たちを指します。彼らは、最低限の生活費を稼ぐための仕事は行いますが、それ以上の出世やキャリアアップ、資産形成には興味を示しません。これは、疲れや収入への不満から「一時的に立ち止まる姿勢」だと表現されることがあります。寝そべり族の行動は、自分たちからは積極的に生産行動をしないという、社会に対する一種の「抗議」です。
ネズミ人間(Rat People)
ネズミ人間は、寝そべり族がさらに「消失」へと進化した形です。 彼らは単に横たわっているだけでなく、「壁の中に消え、見えなくなり、触れられない存在になる」ことを選んでいます。心理カウンセラーは、寝そべり族が一時的に立ち止まる姿勢であるのに対し、ネズミ人間は社会との接点自体を断ち切り、より深い孤立にあると指摘しています。
ネズミ人間の中には、仕事につけたとしても都市でまともな住居を得ることができず、地下などで格安の物件に住み、将来への希望が見えない現実から絶望を感じている人々が多くいます。彼らは怠けているわけではなく、中国の夢を求めて努力してきたにもかかわらず、高すぎる生活費の壁に阻まれ、「働いても地上で暮らせるほど稼げない」という絶望的な状況にいます。
彼らの「低エネルギー」なライフスタイルは、生産性文化、消費主義、そして人間の価値を生産量に結びつける考え方に対する「静かな抵抗の行為」なのです。
「鼠族(そぞく)(Rat Tribe)」との混同を避ける:物理的 vs 精神的

ネズミ人間(Rat People)と混同されやすい言葉に、古くから存在する「鼠族(そぞく)」(Rat Tribe / 中国語: 鼠族 shǔzú)があります。この二つは、ネズミ人間という用語が持つ「物理的な意味」と「比喩的な意味」の違いから、区別して理解する必要があります。
鼠族(Rat Tribe)
鼠族は、物理的な意味で「ネズミのように地下で暮らす人々」を指す造語です。 彼らは、中国の都市部において、高騰する家賃を支払えない低所得の出稼ぎ労働者(民工 mingong)が、冷戦時代に作られた防空壕や地下室などの地下住居に住むことを余儀なくされた集団です。2015年の時点で、北京だけでも推定100万人以上が地下で生活していたという報告があります。
鼠族の住居環境は極めて劣悪です。
- 住居環境
部屋は極端に狭く、多くは15平方メートル以下で、中には4平方メートルしかない押し入れのような部屋もあります。 - 衛生面
壁はベニヤ板で薄く仕切られ、隣の音が筒抜けです。換気が悪く、日光が全くないため、空気はよどみ、カビが生えやすく、健康面で深刻な問題があります。 - 設備
トイレやキッチンは共同で、調理が禁止されている場所もあります。一箇所のトイレを80部屋の住人で共有していた事例も報告されています。
彼らは、地方の農村部には仕事がほとんどないため、チャンスを求めて都会に流入した努力家たちですが、都市戸籍制度(戸籍)の壁にぶつかり、安定した仕事(公務員、学校教師など)や公的サービスを受けられず、低賃金の単純労働を続けるしかなくなっている人々です。彼らの多くは「しっかり働いている」にもかかわらず、都会の生活コストに阻まれ、社会の底辺で生きることを強いられています。
ネズミ人間(Rat People)との関係
SNSで話題の「ネズミ人間」現象は、鼠族のような物理的な地下居住者(「地下に住む人々」という物理的な意味)も含む言葉ですが、特に近年バイラルになったのは、「地下に住んでいなくても、社会的に孤立し、絶望の中で低エネルギーな生活を送る若者」という比喩的な意味のネズミ人間です。
つまり、鼠族が「家賃が高すぎて地下に住むしかない」という経済的・物理的な問題に焦点を当てているのに対し、ネズミ人間は「努力しても報われず、希望を失い、社会との関わりを断つ」という、より精神的・社会構造的な問題の反映であると言えます。
中国社会への影響と政府の強い警戒
ネズミ人間現象は、中国政府が掲げる「中華民族の偉大な復興」や「共同富裕」といったスローガンとは真逆の現実を突きつけるものであり、社会の安定を脅かす存在として政府に強い危機感を抱かせています。
政府による情報統制と対策
中国政府は、無気力や絶望の空気が広がるのを阻止しようと、積極的な情報統制に乗り出しています。政府は、ネズミ人間のような消極的な感情を煽る動画投稿を2ヶ月間集中的に取り締まると発表し、内容によってはアカウント閉鎖などの強硬措置に出るとしています。政府の狙いは、労働者の「努力と継続に対する肯定感を弱める」ことを防ぎ、社会の秩序が乱れるのを防ぐことです。ネズミ人間という言葉自体も、ネット上で削除されたり、別の言葉に置き換えられたりする対象になっています。
政府は若者の雇用支援のために補助金や職業訓練などの対策も行っています。しかし、これらの対策は、若者を「どうやって労働市場に入れるか」という点に焦点を当てているだけで、ネズミ人間たちが感じる「努力しても普通の生活が手に入らない」という絶望の根本原因(高い生活コスト、社会の不平等、報われない構造)に全く対処できていないという決定的なギャップがあります。
社会的な孤立と精神的な影響
ネズミ人間という言葉自体が差別的な意味合いを含んでおり、地上の人からは社会の底辺や犯罪者のように見なされることもあります。彼らは地上の人々と交流がなく、社会的に孤立しています。
研究によると、劣悪な環境、社会的偏見、経済的な苦労の組み合わせは、鬱病や不安障害のリスクを高めることが指摘されています。日光不足や湿度の高い環境も精神健康に悪影響を与えます。この現象は、単なる一過性のトレンドではなく、経済が内部から腐敗していることを示す「手厳しい告発」となっているのです。
世界的視点から見る「ネズミ人間」の未来

ネズミ人間現象は、中国特有の問題ではなく、グローバル化と新自由主義経済の進展がもたらした、東アジア全体、ひいては先進国が抱える共通の問題の現れであるという側面があります。
東アジアの構造的な閉塞感
激しい競争、高い生活費、社会の不平等、努力しても報われないという感覚は、韓国や台湾といった東アジアの他の国々でも深刻化しています。
- 韓国
学歴社会と激しい競争、都市部での住宅価格高騰を背景に、恋愛・結婚・出産を諦める「三放世代」や「N放世代」といった言葉が生まれています。 - 台湾
若者の低賃金や将来への不安が問題になっています。
東アジア地域は、過去の急激な経済成長の過程で、長時間労働や格差といった歪みを生み出し、それがポスト成長期に入って顕在化し、若者を追い詰めているのです。ネズミ人間が感じるような「構造的な絶望」は、今後、形を変えて他の国々にも広がっていく可能性があります。
世代間の断絶と自己変革の可能性
ネズミ人間の増殖は、高齢者世代との間で大きな認識のギャップを生んでいます。年配世代の中には、「昔はもっと大変だった」「努力すれば報われた」「今の若者は根性がない」と批判し、ネズミ人間の態度を利己的だと見なす声も多いです。これは、高度成長期を知る世代と、競争社会しか知らない世代との間の断絶を象徴しています。
しかし、一部の専門家は、この現象を単なる社会的な撤退としてだけでなく、若者が「自分にとって本当の幸せとは何か」を見つめ直す過程であると解釈しています。経済的な余裕がある30代の社会人が、自発的に競争から離脱し、ネズミ人間的な生活を選ぶケースも増えており、これは一時的な「心の休憩」とも言えるでしょう。
長期的にこの生活が続けば、心身への悪影響は避けられませんが、もし彼らがこのままではいけないと思えたなら、スマホから離れる、小さな目標を立てる、散歩に出るなど、些細な一歩から再起の道を探るかもしれません。ネズミ人間という言葉の裏には、不安、諦め、そして再起への小さな希望が混ざり合っているのです。
社会の歪みと「希望の再構築」:ネズミ人間現象が示唆するもの

中国のネズミ人間現象が示唆するように、現代の社会において、若者が感じる閉塞感や無力感は、国境を越えた共通の課題となりつつあります。
世界的では、過度な生産性至上主義への抵抗として、職場で最低限の仕事しかしなくなる「Quiet Quitting(静かな退職)」が注目を集めています。日本でも、生活コストや社会の不確実性を背景に、出世や結婚、マイホームといった従来の成功の形を追求することに意味を見出せない「低欲望社会」や「悟り世代」と呼ばれる若者の傾向、あるいは「引きこもり」といった現象が起きており、ネズミ人間の感覚といくつかの点で共通しています。
このネズミ人間現象は、決して若者個々人の怠惰や精神論の問題ではありません。社会学者の理論が示すように、現代社会が加速し、生産や期待が際限なくスピードアップする中で、その流れから振り落とされた人々の「抵抗」の行為であり、「社会としての問題」の深刻な表れです。ネズミ人間の存在は、経済成長の果実が一部の人に偏り、どれだけ頑張っても普通の生活が遠すぎるという、社会の不平等な構造が引き起こした結果なのです。
中国政府の対応に見られるように、この構造的な絶望に対して、上辺だけの雇用対策や、単なる「動画の取り締まり」といった対症療法では、根本的な解決には至りません。若者たちの心を絶望から救い出すためには、彼らが都市で「まともな暮らし」を営めるだけの経済的保障、社会的な公平性の確保、そして努力が本当に報われるという信頼感、すなわち「希望の再構築」を、国としての責任と対応をもって根本から行っていく必要があるのではないでしょうか。
みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)
SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。