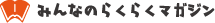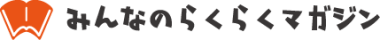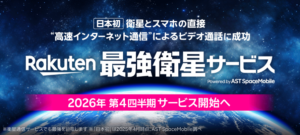スマホが宇宙と直結する時代へ LEO衛星通信の魅力と知っておくべきリスク
【この記事にはPRを含む場合があります】

「スマホの電波が届かない」「旅先や山奥でネットが使えず困った」「災害時に家族と連絡が取れないかもしれない」—そんな通信に関する不安や不便さを感じたことはありませんか。
私たちが普段利用しているインターネットは、地上の基地局や光ファイバーのインフラに大きく依存しています。しかし、そのインフラが行き届かない離島や山間部、広大な海上では、通信の「圏外」というデッドゾーンが広がり続けています。
もし、今お使いのスマートフォンや小型端末が、地球上のどこにいても高速インターネットに直接繋がるようになったら、私たちの生活はどのように変わるでしょうか。
その未来を実現するのが、「LEO通信」という新しい通信技術です。この記事では、イーロン・マスク氏率いるStarlinkやAmazonのProject Kuiper、楽天モバイルが提携するAST SpaceMobileなど、現在、世界中で激しい競争が繰り広げられているLEO通信の最前線をご紹介します。この革新的な技術が私たちの生活にもたらす無限の可能性と、一方で私たちが真剣に考えなければならない宇宙空間の課題、宇宙デブリの問題について、分かりやすくお伝えします。
この記事を読み終わる頃には、通信環境が劇的に進化し、どこにいてもネットが繋がる未来のイメージが明確になり、その未来を支えるために私たちが何をすべきかが見えてくるでしょう。
LEO通信(低軌道衛星通信)とは?基本解説

LEO通信とは、Low Earth Orbit(低軌道)に配置された人工衛星を利用する衛星通信システムのことです。
LEO衛星が実現する革新的な通信の仕組み
衛星通信は従来から存在していましたが、その多くは静止軌道衛星(GEO)と呼ばれる、地上約35,000kmから36,000km上空を周回する大型衛星によって提供されてきました。
これに対し、LEO衛星は地球からわずか数百キロメートルから2,000km未満の低空に配置されます。国際宇宙ステーション(ISS)が約400km上空を周回していることからも、LEOがいかに地球に近いかが分かります。
LEO衛星がこれほど注目される最大の理由は、遅延(レイテンシ)の大幅な低減です。
GEO衛星の場合、信号が衛星まで行って帰ってくる往復遅延時間は600ミリ秒以上かかり、会話やリアルタイムのオンラインゲームには不向きでした。しかし、LEO衛星は地球に近いため、その遅延時間は25ミリ秒から50ミリ秒程度と、既存の光ファイバー通信に匹敵する実用的なレベルを実現しています。
また、LEO衛星は地球の周りを約90分から2時間以内で高速に周回するため、単体で地球上の特定エリアをカバーし続けることはできません。そのため、多数の衛星を連携させて「衛星コンステレーション(衛星群)」として運用することで、地球上のほぼ全域にサービスを提供できる仕組みになっています。
このLEO衛星の特性により、地上の通信インフラが整備されていない山間部、離島、海上、上空の移動体など、これまでは通信が不可能だった場所でも、高速で安定したブロードバンドインターネット接続が可能になるのです。
LEO通信のメリットとデメリット
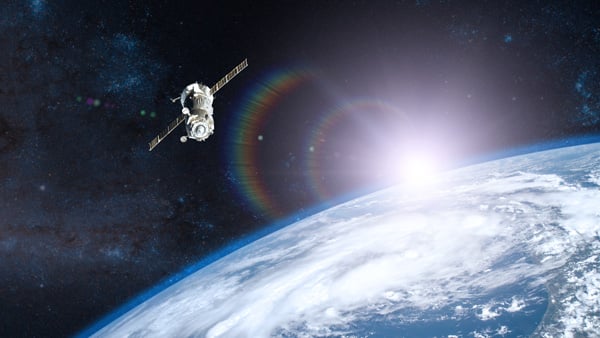
LEO通信が普及することで、私たちの生活には以下のような大きなメリットがもたらされます。
LEO通信のメリット
- 地球上のどこでもブロードバンド接続が可能に
地上の基地局に依存しないため、光回線が引けないへき地や海上、災害で地上インフラが停止した場合でも通信手段が確保できます。 - 高速かつ低遅延な通信
GEO衛星に比べて通信速度が速く、遅延が少ないため、動画視聴やオンライン会議、遠隔医療、自動運転車など、リアルタイム性が求められる用途での利用が期待されています。 - 迅速な展開と復旧
光回線のような大規模な敷設工事が不要で、専用端末(アンテナ)さえあれば、数分以内にインターネット接続が可能です。災害発生時など、緊急を要する場面でも迅速に通信環境を復旧できるのは大きな強みです。
LEO通信のデメリット
- コストが割高
専用端末の初期費用に加え、月額料金も従来の光回線やモバイルWi-Fiサービスと比較して高額になる傾向があります。 - 設置場所に制限がある
衛星と直接通信するため、アンテナ(端末)の上空の視界が確保されている必要があります。地下や、木々や建物に囲まれた場所では、通信が不安定になったり、接続できなかったりする可能性があります. - 天候の影響を受ける
厚い雲や激しい雨、雪などの悪天候時には、通信品質が低下することがあります。 - 衛星の寿命が短い
LEO衛星は軌道上のわずかな大気抵抗(大気による引きずり)を受けるため、静止軌道衛星よりも寿命が短く(約5~7年)、軌道を維持するための推進力が必要であり、絶えず衛星の打ち上げと入れ替えを行う必要があります。
LEO通信の主要プレイヤー:各サービスの独自戦略
LEO通信の市場では、イーロン・マスク氏のStarlinkが先行していますが、Amazon、楽天モバイル(AST SpaceMobile)、そしてシャープといった強力なライバルたちが独自の技術と戦略で追随しています。
Starlink (スターリンク)

(出典:Starlink)
Starlinkは、アメリカの民間宇宙開発企業SpaceX社が提供する衛星インターネットサービスです。イーロン・マスク氏が創業者として知られています。
Starlinkの主な特徴
- 圧倒的な衛星数による先行優位
Starlinkは2024年時点で約6,000機もの衛星を低軌道に展開しており、競合に対して圧倒的なリードを保っています。将来的には12,000個以上の衛星を打ち上げる計画があります。 - 専用端末「Dishy」と携帯性
インターネット接続には、ユーザーが設置する専用の受信アンテナ「Dishy」とルーターが必要です。 特に、Starlink Mini(スターリンク ミニ)は、従来のアンテナよりも大幅に小型化・軽量化(約1.1kg)され、バックパックに入るほどのコンパクトさで、キャンプや車中泊、災害時の持ち運びに対応しています。最大150Mbpsの通信速度を実現し、最大128台のデバイスに同時接続できる点も強みです。 - 日本国内での展開
Starlinkは2022年に日本でもサービス提供を開始し、KDDI、ソフトバンク、NTTドコモなどの国内キャリアも法人向けプランや基地局への活用で提携を進めています。2024年1月1日の能登半島地震では、迅速に提供されたStarlink端末が通信手段として活用され、その有用性が実証されました。
AST SpaceMobile (ASTスペースモバイル)

(出典:AST SpaceMobile)
AST SpaceMobileは、アメリカのAST SpaceMobile社と日本の楽天モバイル株式会社が共同で開発を進めているNTN(非地上系ネットワーク)サービスです。
AST SpaceMobileの主な特徴
- 世界初の「スマホ直結型ブロードバンド」
AST SpaceMobileの最大の革新は、専用端末やアンテナを必要とせず、現在使用中の市販の携帯電話やスマートフォンがそのまま衛星と直接通信できる点です。これは世界初の「宇宙ベースのセルラーブロードバンドネットワーク」を目指す構想です。 - 巨大な衛星と高度な技術
地上のスマートフォンからの微弱な電波をはるか上空で捉えるため、衛星には非常に巨大なアンテナが必要です。試験衛星「BlueWalker 3」は、展開するとテニスコートの約4分の1の面積に相当する64m²のアンテナを搭載していました。この技術を実現するための特許は3,500件以上に上るとされています。 - ビジネスモデルは「ホールセール(卸売り)」
Starlinkが一般消費者へ直接サービスを販売するのに対し、AST SpaceMobileは、楽天モバイルやAT&T、ボーダフォンなど、世界の携帯電話会社(MNO)に対してインフラを提供するホールセールモデルを採用しています。これにより、AST SpaceMobileは、提携する携帯電話会社が持つ世界で合計20億人以上に上る顧客基盤をそのまま活用できるという効率的な戦略をとっています。 - 日本でのサービス開始予定
楽天モバイルとAST SpaceMobileは、2025年4月に日本国内で初めて低軌道衛星と市販スマートフォン同士のエンドツーエンドでの直接通信によるビデオ通話に成功したと発表しました。日本国内での商用サービス開始は2026年第4四半期(10月〜12月)を目指しています。
Amazon Project Kuiper (アマゾン プロジェクト・カイパー)
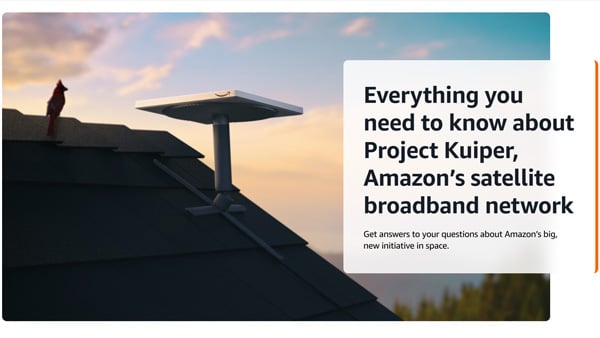
(出典:Amazon)
Project Kuiperは、Amazonが手掛ける大規模なLEO衛星ブロードバンドネットワーク計画です。Starlinkの最大の競合の一つと目されています。
Project Kuiperの主な特徴
- 大規模なコンステレーション計画
Project Kuiperは、今後10年間に3,236機を超える衛星を低軌道に打ち上げる計画を発表しています。 - AWSとの連携
Amazon Web Services(AWS)という強力なインフラ基盤を持っていることが大きな強みです。多くのウェブサービスがすでにAmazonのデータセンターでホストされているため、衛星ネットワークとAWSを連携させることで、高性能で統合されたサービス提供を目指しています。 - 低コストでの提供を目指す
Project KuiperはStarlinkよりも低コストでのサービス提供を目指しているとされています。ただし、Starlinkがすでに数千機の衛星を軌道に乗せているのに対し、Kuiperはまだ立ち上げの初期段階であり、今後数年間で数多くの打ち上げを迅速に行う必要があります。
> Amazon Project Kuiper公式ページはこちら
Sharp LEO衛星通信ユーザーターミナル

(出典:SHARP)
シャープは、独自のアンテナ技術を活かしたLEO衛星通信ユーザーターミナルを開発しています。
Sharp LEO衛星通信ユーザーターミナルの主な特徴
- 移動体での安定通信に特化
このターミナルは、揺れや振動の大きい船舶、自動車、建機、農機、ドローンなど、さまざまな移動体での利用を想定して設計されています。 - 独自のビーム制御技術
地球の周りを高速で移動するLEO衛星を正確に追跡するため、シャープ独自のビーム制御技術が用いられています。これにより、船舶の揺動や車両の高速走行、旋回といった不安定な環境下でも、途切れにくい安定した通信状態を維持することが可能です。 - 小型・軽量化と5G NTN対応
スマートフォンの開発で培った小型・軽量化技術を応用しており、一般的な衛星通信アンテナでは設置が難しかった環境でも利用できるように開発されています。 また、5G NTN(非地上系ネットワーク)通信に対応しており、将来的に衛星通信がセルラー通信と同じ5G通信方式を採用すれば、地上のセルラー通信と衛星通信をシームレスに切り替えることが可能になります。
> Sharp LEO衛星通信ユーザーターミナル公式ページはこちら
LEO通信が切り拓く未来の生活と、私たちが考えるべき課題
LEO通信は、地理的な制約や災害によるインフラの損壊といった、従来の通信が抱えていた根本的な問題を解決する可能性を秘めています。
どこでも繋がる未来のメリット
LEO通信が普及すると、私たちの生活には以下のような変化が起こるでしょう。
究極のモバイル環境の実現
Starlink Miniのような持ち運び可能な小型端末や、シャープが開発中のような移動体向けターミナルの登場により、キャンピングカーでの長期滞在、山間部でのリモートワーク、遠洋漁業を行う船舶内での快適なインターネット接続が当たり前になります。
特に、AST SpaceMobileのように、特別な専用機器なしでスマートフォンが直接衛星に繋がる技術が普及すれば、電波の届かない登山中やへき地でも、家族や仲間に安否情報を届けたり、緊急時にSMSを送ったりすることが可能になります。
地球規模での格差解消と経済活動の拡大
現在、世界の人口の数億人が信頼できるインターネットアクセスを欠いており、この「グローバル・カバレッジ・ギャップ」は深刻な課題です。LEO通信は、こうした通信の不便な地域でも高速インターネットを提供することで、教育や医療の遠隔化を促進し、情報格差の解消に大きく貢献します。
また、船舶や航空機など、これまで通信が困難だった移動体でのブロードバンド接続が可能になることで、海運・航空・農業・建設といった様々な分野で新たなビジネスチャンスが創出されます。
災害に強い通信インフラの構築
地震や台風などの大規模な災害が発生した場合、地上の基地局や光ファイバー網は大きな被害を受け、通信が途絶することがあります。LEO通信はインフラが「空」にあるため、地上の災害の影響を受けません。
これにより、緊急時にも安定した通信手段が確保され、被災地と外部との連絡、救助活動、インフラ維持に不可欠な手段となります。
LEO衛星の密集がもたらす「宇宙デブリ」の脅威

LEO通信がもたらす豊かな未来の裏側で、私たちは宇宙空間における深刻な環境問題に直面しています。それが、宇宙デブリ(スペースデブリ)の問題です。
LEO衛星は、その低軌道という特性上、地球の周りを高速で周回しています。現在、LEO通信サービス各社は数千機、将来的には数万機もの衛星を打ち上げる計画を立てています。
このLEO軌道は、すでに役目を終えた人工衛星やロケットの残骸、微細な塗料の破片など、さまざまなデブリで混雑しています。
- デブリの脅威
科学者たちは、10cmを超えるデブリが約34,000個存在し、これらが時速28,000km以上という極超音速で飛んでいると推定しています。たとえ小さなデブリであっても、衛星や宇宙船に衝突すれば致命的な損傷を与える可能性があります。 - ケスラーシンドロームのリスク
衛星の打ち上げ数が増加し、デブリの密度が高まることで懸念されているのが、ケスラーシンドロームです。これは、一度衝突が起きると、その破片がさらに別の物体に衝突し、連鎖的にデブリが増殖していくという現象です。この現象が現実化すれば、将来的に一部の宇宙空間が利用不可能になる可能性があり、宇宙探査にとって最大の障害となり得ます。 - 短命なLEO衛星
LEO衛星の寿命は約5年から7年と短く、運用終了後に大気圏に再突入して燃え尽きるように設計されているものの、常に新しい衛星が大量に打ち上げられ続けるため、軌道上の混雑は増す一方です。
LEO通信企業もこの問題の重要性を認識しており、Starlink衛星には寿命が尽きた際に軌道から離脱するためのホールスラスタが搭載されています。AmazonのProject Kuiperも、軌道デブリのリスクを最小限に抑えるように設計されていると表明しています。
しかし、通信インフラの利便性が向上する一方で、宇宙環境を持続可能に保つための国際的な協力と、デブリを削減・管理するための技術開発(宇宙交通管理)が、これからのLEO通信の発展にとって不可欠な課題なのです。
空と地球が一体となる、次世代インターネットがもたらす安心と豊かさ

LEO通信は、単なるインターネット回線の選択肢の一つではなく、人類が地球上のあらゆる場所で「繋がる」ことを可能にする、社会インフラの革命です。
Starlinkのような先行者が実現した圧倒的なカバレッジ、AST SpaceMobileが目指すスマートフォン直結の利便性、そしてシャープが推進する移動体向けの安定した通信技術は、私たちが光ファイバーの整備を待つ必要のない未来を現実のものにしつつあります。特に、楽天モバイルとAST SpaceMobileによる2026年中のサービス開始は、日本の通信市場に大きなインパクトを与えるでしょう。
今後、LEO通信がさらに一般化していくことで、私たちは災害時にも安心できる確かな通信手段を手に入れ、趣味のキャンプや旅行、仕事に至るまで、生活の自由度を大きく広げることができます。
しかし、私たちはこの利便性の恩恵を享受すると同時に、その基盤である宇宙空間の環境保全という重大な責任も担っています。
LEO通信の進化は、私たちに「どこでも繋がる自由」をもたらしますが、同時に「宇宙の持続可能性」という課題も突きつけます。私たちは、この新時代のインターネットがもたらす安心と豊かさを享受しつつ、宇宙デブリ問題の解決に向けた取り組みにも関心を持ち、持続可能な未来のために次世代の通信技術を見守っていく必要があるのです。
みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)
SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。