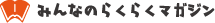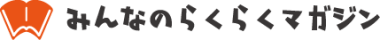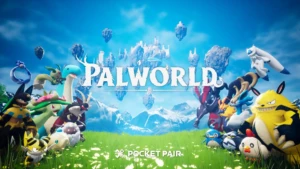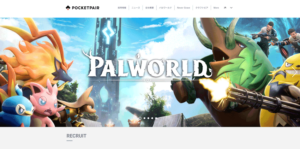任天堂のパルワールド訴訟、なぜアメリカで形勢逆転の危機?
【この記事にはPRを含む場合があります】
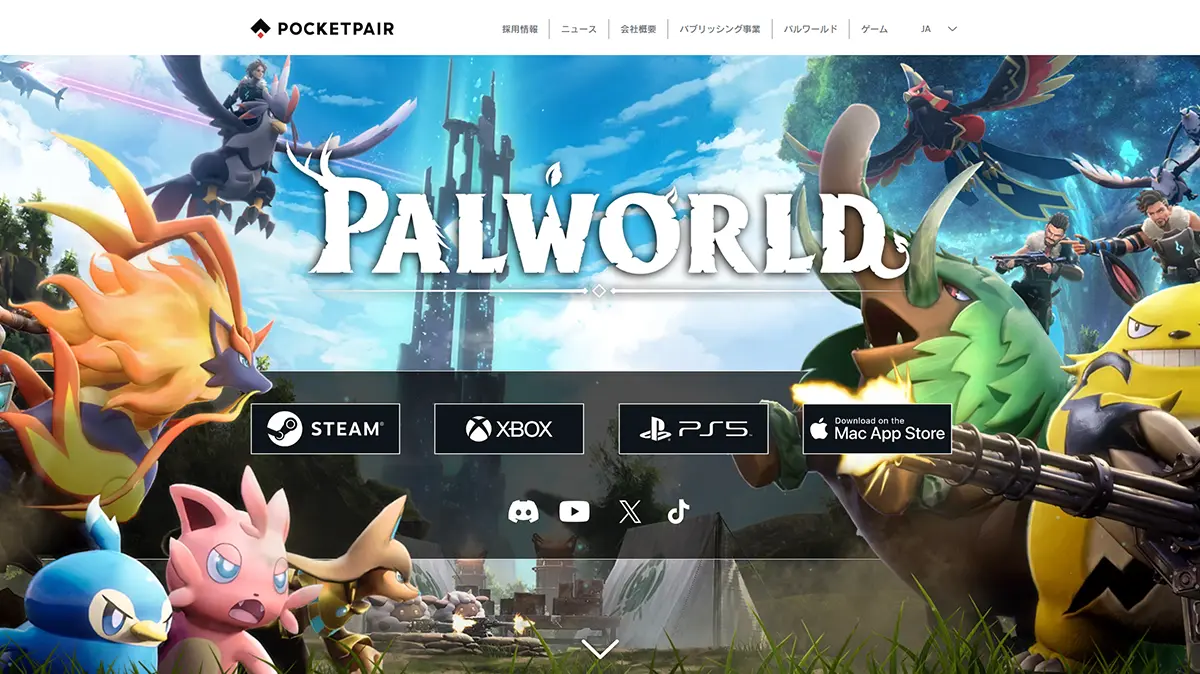
ゲーマーの間で今、最も注目されているニュースといえば、大ヒットゲーム『パルワールド』を巡る任天堂とポケットペアの特許権侵害訴訟ではないでしょうか。発表当初から「ポケモンに似ている」と話題になり、単なるパクリなのか、それとも新時代のイノベーションなのか、世界中で議論が巻き起こりました。多くの人が「任天堂の最強法務部が動いたら終わりだ」と感じたかもしれません。しかし、この複雑な特許戦争は、単なる一企業の争いにとどまらず、ゲーム業界の創造性と特許制度のあり方そのものを問う、世界的な論争へと発展しています。特に、アメリカでは任天堂が不利になるかもしれない、非常に異例な事態が発生しています。この記事では、なぜこの裁判が起こったのか、日米での最新の法廷戦況、そしてこの訴訟がゲーム業界全体にどのような影響を与えるのかを、わかりやすく解説していきます。複雑な特許や裁判の話題をスッキリ理解し、今後の行方を見通すヒントをぜひ掴んでください。
大ヒットの裏側!「パルワールド」ってどんなゲーム?

(出典:PR TIMES)
『パルワールド(Palworld)』は、日本のゲーム開発会社であるポケットペアが開発・提供する、オープンワールド・サバイバルクラフトゲームです。
このゲームは、不思議な生物「パル」が生息するパルパゴス島を舞台に、プレイヤーがパルを捕獲し、拠点建設や戦闘、サバイバル生活を送ることを目的としています。
リリースは2024年1月19日(早期アクセス版)でしたが、その人気は爆発的でした。わずか1ヶ月で総プレイヤー数は2,500万人を突破し、Steam版だけで1,500万本、Xbox版では1,000万ユーザーに到達する大ヒット作となりました。特にアメリカでは爆発的なヒットを記録しています。
ゲームの特徴として、プレイヤーは「スフィア」という道具を使ってパルを捕獲し、パルを戦闘に利用したり、建築や資材集めを手伝わせたり、さらには食用にしたり、売却したり、強制労働させたりといった、従来のモンスター収集ゲームにはないダークな要素を持っていることが話題になりました。
発表当初から「銃があるポケモン(Pokémon With Guns)」という愛称で呼ばれていましたが、ポケットペアのCEOは、全体的なゲームコンセプトは『ARK: Survival Evolved』から、サバイバルの仕組みやタスクは『Rust』から影響を受けており、パルのデザインも『ドラゴンクエスト』から着想を得ていると述べています。ゲーム体験自体は、従来のコマンドバトル形式のポケモンとは異なり、サバイバルゲームに近いです。
ちなみにポケットペアは2015年創業のインディーゲーム開発会社で、2024年7月にはソニー・ミュージックエンタテインメントとアニプレックスとの合弁会社「パルワールドエンタテインメント」を設立し、IP(知的財産)の世界展開を図っています。
なぜ裁判になった?問題は「パクリ疑惑」ではなく「特許」だった

『パルワールド』がリリースされた直後から、一部のパルのデザインが『ポケットモンスター』シリーズのポケモンに酷似しているという著作権侵害(パクリ)疑惑がSNSやメディアで大きな論争となりました。
これに対し、株式会社ポケモンは2024年1月25日に、特定のゲーム名を挙げずに「他社ゲームに関する問い合わせについて」という声明を発表し、知的財産権の侵害行為について調査を行い、適切な対応を取る意向を表明しました。
そして、早期アクセス開始から約8か月後の2024年9月18日、任天堂と株式会社ポケモンは、ポケットペアに対し、著作権ではなく「特許権の侵害」を理由とする訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
任天堂側が求めているのは、侵害行為の差し止めと損害賠償(ポケモン社と任天堂それぞれ最低500万円、合計1000万円以上)です。
訴訟の争点となった「ゲームメカニクス特許」
ポケットペアの報告により、訴訟の争点となっている日本の特許は以下の3件です:
- 特許第7493117号(捕獲・戦闘関連):
- アイテム(パルを捕獲するスフィアなど)を投げて、フィールド上のキャラクターを捕獲したり、戦闘キャラクタを登場させて戦闘を開始させたりする機能に関する特許。
- 特許第7545191号(投擲アイテム関連):
- 複数の捕獲アイテムから選択したものを、照準方向に向けて放つことに関する特許。
- 特許第7528390号(搭乗・移動関連):
- プレイヤーが空中にいるときに操作入力を行うと、搭乗キャラクタ(飛行パルなど)に搭乗させ、空中を移動可能な状態にする機能(フライングスタートのメカニクス)に関する特許。
パルワールドを狙い撃ち?発売後に取得された特許
興味深いのは、これらの特許は全てパルワールドの早期アクセス発売後(2024年内)に登録されている点です。
しかし、これらは2021年の親特許(先行出願)に基づいて「分割出願」という手法を用いて取得された特許です。この手法は、元の出願の範囲内であれば、競合他社の製品(パルワールド)の仕様に合わせて特許の請求項を修正し、後出しじゃんけんのように権利を主張できる点で、特許権の強さをブーストする戦略とされています。
任天堂側が特許権侵害で提訴した背景には、これらの特許がゲーム画面を確認するだけで侵害の有無を判断しやすいため、著作権侵害を立証するよりも訴訟を進めやすいという狙いがあったと見られています。
任天堂の本当のゴールは「金銭」ではない
任天堂がポケットペアに請求している損害賠償額は最低1,000万円と、大ヒット作の売上(推定692億円)を考えると、一見すると少額です。
このことから、任天堂の本当の目的は金銭的な賠償よりも、「侵害行為の差し止め」、つまり『パルワールド』からパルを捕獲するメカニクスや、特定の搭乗・召喚方法といった根幹のシステムを削除させることにあると指摘されています。
もし任天堂が勝訴し差し止めが認められれば、『パルワールド』は大幅な仕様変更を余儀なくされ、ゲーム体験に大きな影響を与えることになります。
特許ゴロって?ゲームシステム特許の功罪
任天堂が、大ヒットした他社製品の発売後に分割出願した特許を武器に訴訟を起こしたことに対し、海外メディアや一部の専門家からは「特許ゴロ(パテントトロール)のような振る舞い」ではないかという厳しい意見が出ています。
業界の創造性を阻む「ザル特許」
特許法は、新しい発明に対して独占権を与えることで、技術革新を奨励する制度です。しかし、ゲーム業界において、ある程度の時間が経過したアイデアや、複数の既存技術の組み合わせを特許で独占することには大きな問題があります。
ポケットペア側は、任天堂が訴訟の根拠とする特許について、発明の時点で既に『ARK: Survival Evolved』や『FF14』などの有名タイトルで使われていた「先行技術」が存在しており、新規性や進歩性がない(誰もが容易に思いつくアイデアである)と反論しています。
特に、任天堂の特許は2022年と比較的新しいにもかかわらず、そのアイデアが「なぜ特許庁で認められてしまったのか」という疑問の声も上がっており、特許庁が安易に特許を認めてしまう「ザル特許」の問題や、日本の特許法そのものの欠陥が指摘されています。
一部の弁理士からは、任天堂の今回の訴訟は、法的に勝ち目が薄い、あるいは特許庁の怠慢で得られた偶然の権利を奇貨として、企業の資金力を用いて競合他社の表現行為を差し止める「SLAPP訴訟」(恫喝訴訟)に該当するのではないかという見解も示されています。
20年で失効する「アイデア」の権利
特許権の存続期間は原則20年です。これは、発明の独占期間を制限することで、誰もがそのアイデアを利用して次の発明を生み出すことを促すためです。
しかし、ゲーム業界の歴史が長い大手企業が、過去のゲームのシステムやアイデアを特許で囲い込み、他社の参入を阻止する動きは、業界全体のイノベーションを阻害します。
『ポケットモンスター』の原始的なアイデア(モンスターボールで捕まえて育成・戦闘させるRPG)は既に30年以上前の作品に由来しており、本来であれば、そのアイデア部分は「皆の財産」となり、誰でも商用利用できるはずだという意見も存在します。
【時系列】訴訟勃発から最新情報までを追う
任天堂とポケットペアを巡る訴訟は、日本とアメリカの法廷で並行して、異例の展開を見せています。
| 年月日 | 主な出来事 | 関連国 |
|---|---|---|
| 2021年6月5日 | Pocketpairが『パルワールド』を発表。 | 日本 |
| 2023年5月26日 | パルを捕獲する「スフィア」の詳細トレーラーが公開され、ポケボールとの類似性が指摘される。 | 日本/世界 |
| 2024年1月19日 | 『パルワールド』早期アクセス開始、爆発的ヒット(Xbox、PC)。 | 日本/世界 |
| 2024年1月24日 | 任天堂が知的財産権侵害の可能性について調査する声明を発表。同日、任天堂は『パルワールド』のポケモンMODに関するDMCA申請を行い、関連MODが削除される。 | 日本/世界 |
| 2024年7月10日 | Pocketpairがアニプレックス、ソニー・ミュージックエンタテインメントと共同で「パルワールドエンタテインメント株式会社」を設立。 | 日本 |
| 2024年9月18日 | 任天堂と株式会社ポケモンが、東京地方裁判所にPocketpairを特許権侵害で提訴。 | 日本 |
| 2024年9月19日 | Pocketpairが訴訟に対し公式声明を発表。 | 日本 |
| 2024年11月8日 | Pocketpairが、任天堂とポケモン社が合計1,000万円(それぞれ最低500万円)の損害賠償を求めていることを公表。 | 日本 |
| 2024年11月30日 | 『パルワールド』がパルスフィアを使ったパルの召喚機能を削除するパッチ(v0.3.11)をリリース(予防的措置)。 | 日本 |
| 2025年2月21日 | ポケットペアが準備書面を提出し、先行技術(MODなど)の存在を主張。 | 日本 |
| 2025年5月8日 | 『パルワールド』がパッチ v0.5.5 を配信し、予防的措置としてグライダーパルによる滑空の仕様を変更(パル自体ではなくアイテムを使用する方式に)。同日、Pocketpairは訴訟に関する声明で、この変更が訴訟対応に伴うものであることを明かした。 | 日本 |
| 2025年10月17日 | 任天堂の主要な特許出願(パルワールド関連)に対し、日本特許庁(JPO)が「進歩性なし」として拒絶理由通知を発行。 | 日本 |
| 2025年11月3日 | 米国特許商標庁(USPTO)長官が職権により、任天堂のゲームメカニクスに関する特許(397特許)の再審査を命令。 | アメリカ |
予防措置として「仕様変更」を実施
予防措置として「仕様変更」を実施2024年11月30日にスフィアを投げてパルを召喚する機能が削除されたパッチ v0.3.11 の後も、ポケットペアは訴訟の進行状況に左右されることなく、開発と配信を継続できるようにするため、予防的な措置として仕様変更を加えてきました。
2025年5月8日に配信されたパッチ v0.5.5 では、グライダーパルによる滑空について、パル自身ではなくアイテムのグライダーを使用して行う方式に変更されました。この変更は、実際のプレイ体験への影響が最小限になるよう配慮されているものの、訴訟対応に伴う仕様変更だったことが明かされています。
ポケットペアは、係属中の訴訟において、従前の仕様が特許を侵害していないことが明確に認められるまで、変更した仕様を元の仕様に戻すことはないと明言しています。
米国と日本で続く「特許の正当性」への疑問
特に2025年後半には、日米両国の特許審査機関から、任天堂の訴訟戦略の根幹を揺るがす動きが相次ぎました。
- 日本特許庁による拒絶理由通知(2025年10月17日)
任天堂の特許出願の一つが、日本特許庁(JPO)によって「進歩性が欠如している」として拒絶理由通知を受けました。拒絶の理由として、JPOは『ARK: Survival Evolved』や『モンスターハンター4』、さらには任天堂自身の『ポケモンGO』など、複数の先行技術が存在していたことを引用しています。この通知は、訴訟で争点となっている特許群と「兄弟」の関係にあるため、任天堂の主張の正当性が問われる大きな出来事となりました。 なお、この通知は最終的な「却下(拒絶査定)」ではないため、任天堂には2か月以内に対応(補正や意見書の提出)を行う余地が残されています。 - 米国特許庁長官による異例の再審査命令(2025年11月3日)
米国特許商標庁(USPTO)の長官ジョン・A・スクワイヤーズ氏が、任天堂の「召喚キャラクターを戦わせる特許」(397特許)について、職権に基づき再審査を命令しました。USPTO長官が自ら再審査を命じるのは極めて異例の事態であり、過去10年以上なかったことだとされています。 長官が再審査を命じた根拠は、以下の二つの先行技術(Prior Art)が既に存在していたことです:- 2002年にコナミが出願した特許(サブキャラクターを自動または手動で戦わせるもの)。
- 2019年に任天堂自身が出願した特許(2020年に公開)。
長官は、これらの先行技術が「特許性に関する新たな重大な疑問」を提起すると判断しました。この再審査命令は、任天堂の訴訟戦略の信頼性を大きく揺るがす「大打撃」だと見られています。
USPTO長官がこのような稀な行動を取った背景には、ゲームメディアや法律専門家からの「公の怒り(public outrage)」が影響したとされています。この再審査命令は、任天堂の訴訟戦略の信頼性を大きく揺るがす「大打撃」であり、アメリカでは任天堂の特許が最終的に無効になる可能性が高いと専門家は見ています。
日本でも「進歩性なし」の拒絶通知
一方、日本においても任天堂の特許申請は課題に直面しています。
任天堂がパルワールド訴訟に関連して分割出願した特許の一つ(2024-031879号)に対し、日本特許庁(JPO)から「拒絶理由通知」が出されました。
拒絶の理由は「進歩性の欠如」(その技術分野の通常の知識を持つ人が容易に発明できる)とされ、先行技術として以下のゲームが引用されています。
- 『ARK: Survival Evolved』
- 『モンスターハンター4』
- 『クラフトピア』(ポケットペアの前作)
- 『ポケモンGO』(任天堂自身のタイトル)
拒絶理由通知は、特許審査の過程で一般的な手続きであり、直ちに特許が却下される「拒絶査定」ではありません。任天堂は今後2か月以内に、請求項の修正や意見書の提出などで対応することが可能です。
しかし、この拒絶通知は、訴訟で主要な争点となっている特許群と「兄弟」の関係にあるため、日本の特許庁ですら、任天堂が主張するゲームメカニクスが「独自で新しい発明ではない」と判断したことは、任天堂の訴訟における優位性を損なう大きな出来事だと言えます。
キャラクターデザインの「著作権侵害」は問題ないのか?

『パルワールド』のキャラクターデザインが、なぜ著作権侵害ではなく特許権侵害で争われているのかは、多くの人の疑問点です。
任天堂側が著作権ではなく特許権を選択した最大の理由は、著作権侵害の立証が非常に難しいからです。
アイデアには著作権がない
著作権が保護するのは、小説や絵画のような「表現されたもの」であり、特許権が保護する「発明(アイデア)」とは異なります。
著作権法上、「コンセプトには、著作権はない」という大原則があります。ゲームのモンスターが可愛らしい、ボールを使って捕獲するといったアイデアの段階にとどまる類似性であれば、著作権の侵害とは言えません。
弁護士の意見によれば、『パルワールド』のキャラクターはポケモンのデザインを参考にしている可能性はあっても、具体的な表現として一致しているかの立証は厳しく、「ポケモン側がデザインの侵害について主張するには、厳しいものになるだろう」と指摘されています。アセットの盗用が証明されない限り、「怠惰なデザイン」であっても、法的には盗用とは認められません。
任天堂が著作権を避けたもう一つの理由
任天堂が特許権で訴訟を起こしたことの裏には、「敗訴リスク」を回避する狙いがあったという穿った見方も存在します。
もし任天堂が著作権侵害で訴訟を起こし、敗訴した場合、「これほど似通っていても著作権侵害にならない」という判例ができてしまい、今後、他のクリエイターがより自由にポケモンのアイデアを流用できるようになる、という結果を招きかねません。
特許権であれば、仮に敗訴しても、「偶然通ってしまったザル特許が消えるだけ」で済み、訴訟を通じてポケットペアに十分なダメージ(差し止め要求や訴訟対応のコスト)を与えられるため、任天堂にとっては最初から「負けてもいい訴訟物」として特許権を選んだのではないかという見解もあります。
MOD文化も巻き込まれた?ゲーム業界の創造性への影響
任天堂とポケットペアの訴訟は、単に両社の問題に留まらず、ゲーム業界全体、特にクリエイター文化に波紋を広げています。
広範なゲームメカニクスへの脅威
任天堂が特許で独占しようとしているゲームメカニクス(召喚して戦わせる、特定の移動方法など)は、もし認められれば、『ペルソナ』『デジモン』『World of Warcraft』など、多くのゲームに影響を与える可能性があります。
このような広範囲なゲームプレイの仕組みを一企業が独占することは、業界のイノベーションや創造性を著しく阻害する「根本的な脅威」となり得ます。
過去には、ワーナー・ブラザースの『シャドウ・オブ・ウォー』に搭載されていた「ネメシスシステム」が特許で保護された結果、他のゲームで類似のシステムが使えなくなった事例があり、ゲームシステム特許の強すぎる独占力には懸念が示されています。
先行技術としての「MOD」が引き起こした論争
ポケットペアは、自社の特許侵害否定の根拠として、任天堂の特許に該当するゲームメカニクスが、過去の非公式なMOD(例: 『ダークソウル3』のポケモン化MOD「ポケットソウルズ」)によって既に実現されていた、すなわち「先行技術」であると主張しています。
これに対し任天堂は、MODは「単体で成立するもの」ではなく、元のゲームがなければ動作しないため、独立した技術とは言えず先行技術としては認められないと反論しています。
この任天堂の反論は、著作権侵害を前提としたMOD制作者の活動を黙認してきたゲーム業界の暗黙の了解(グレーゾーン)を崩しかねないとして、一部のPCゲーマーやMOD制作者コミュニティから、MOD文化を危険に晒す行為だとしてポケットペア側への批判も出ています。もしMODが先行技術として認められることになれば、今後はMOD制作者が特許侵害で訴えられるリスクが高まり、ゲーム会社がMODを厳しく規制する動きにつながる可能性があります。
裁判の行方と業界の未来:特許が「足枷」にならないために
任天堂とポケットペアの訴訟は、特にアメリカでの再審査命令や、日本での拒絶理由通知という形で、任天堂側が当初予想していたよりもはるかに難しい局面を迎えています。
任天堂は現在、日本特許庁から受けた拒絶理由通知に対し、請求項の修正や意見書の提出を通じて特許の再登録を目指すと見られます。しかし、米国特許庁長官による異例の再審査命令や、先行技術の存在が明確に示されたことで、任天堂が主張する特許の正当性自体が大きく揺らいでいるのが現状です。
ポケットペアは、予防的措置としてゲームの仕様変更を行うなど、訴訟の進行に影響を受けながらも、特許侵害を否定し、徹底抗戦の構えを崩していません。この裁判の結末は、和解(過去のコロプラ訴訟の例では33億円での和解例がある)になる可能性もあれば、任天堂の特許が無効になる可能性も十分にあり得ます。
ゲームシステム特許の未来
この訴訟が浮き彫りにしたのは、ゲームシステムは似たようなものがいろんなゲームで使われているので、特許としてどう扱っていくのかは難しいという根本的な問題です。
特許制度は本来、イノベーションを促進するためのものですが、ゲーム業界の歴史や、特許取得の容易さ、権利期間の長さ(20年)を考えると、特許が新しいゲームの足枷になるのは問題であり、今回に関しては任天堂が少しやりすぎたのではないかという批判もやむを得ません。
ある程度特許を認めるのは必要ですが、やりすぎは良くないというバランスが求められます。ゲーム業界の発展のためには、特許権の行使がインディー開発者や新興企業にとって実質的な参入障壁とならないよう、見直しが必要です。
具体的には、米国の専門家は、ゲーム特許の審査基準を厳しくして「容易に思いつくアイデア」には特許を与えないこと、あるいは差止請求を認めず賠償金での解決に限定し、特許を許可する側がゲーム業界の歴史や先行技術を把握しておく必要もあるのではないか、といった提言を行っています。
この裁判は、単なるゲームの勝敗を超え、今後のクリエイターたちが自由に創作活動を行うための「ルール」を決める重要な一歩となるでしょう。
みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)
SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。