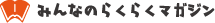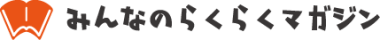【いつから?】Wi-Fi 8ルーターがVR/AR、iPhoneの接続を劇的に変える
【この記事にはPRを含む場合があります】

自宅で、オフィスで、あるいは移動中に、Wi-Fiの調子が悪くてイライラした経験はありませんか?
高画質の動画ストリーミング中に画面が固まったり、オンラインゲーム中に一瞬ラグが発生して負けてしまったり、家族全員が同時にインターネットを使うと通信が不安定になったり……。私たちは日々、高速な通信を期待しているのに、無線という性質上、接続の「不安定さ」や「途切れやすさ」という不安が常に付きまとっています。
しかし、もうそんな悩みとはお別れできるかもしれません。次世代のWi-Fi規格である「Wi-Fi 8」は、これまでのWi-Fiが追い求めてきた「最高速度の更新」ではなく、「途切れない安定性」という全く新しい価値観を最優先に開発が進められているからです。
この記事では、最新の通信技術の動向を踏まえ、Wi-Fi 8(802.11bn)が具体的に何を変え、いつ頃私たちの手元に届くのか、そして今主流のWi-Fi 7と比べて何がすごいのかを、分かりやすくご紹介します。最新のiPhoneやAndroid、次世代のVR/ARデバイスの性能を最大限に引き出したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
- Wi-Fi 8ってなに?「超高信頼性」がもたらす無線通信の革命
- 速度の限界突破ではない?Wi-Fi 7とWi-Fi 8の決定的な違い
- 【いつから?】Wi-Fi 8ルーターはいつ日本で使えるようになる?
- 「途切れない」を実現するWi-Fi 8の革新的新技術
- 1. マルチAP連携 (Multi AP Coordination)
- 2. 動的サブチャネル操作 (DSO: Dynamic Sub-Channel Operation)
- 3. 強化された長距離通信 (ELR) と分散リソースユニット (DRU)
- 4. シームレスローミング(Make Before Break)の改善
- 5. 新たなMCS値(Unequal Modulation/UEQM)
- 家庭内の不安定通信はもう卒業!Wi-Fi 8は本当に必要?
- VR/AR、IoT、産業を変える!Wi-Fi 8が世の中にもたらす未来
- 「UHR」の恩恵と注意点!メリットとデメリットをチェック
- 次世代のWi-Fiは「繋がり続ける安心」を約束してくれる
Wi-Fi 8ってなに?「超高信頼性」がもたらす無線通信の革命
Wi-Fi 8は、技術的には「IEEE 802.11bn」と呼ばれる次世代の無線LAN規格です。
この規格を特徴づけるキーワードは、「超高信頼性」(Ultra High Reliability、略してUHR)です。
過去のWi-Fi規格、特にWi-Fi 6やWi-Fi 7が、チャンネル幅の拡大や変調方式の進化によって「最高速度の向上」に注力してきたのに対し、Wi-Fi 8は、信号の信頼性と一貫したパフォーマンスの実現に主眼を置いています。
この「超高信頼性(UHR)」という目標には、具体的に以下の定量的な改善が含まれています。
- 実効スループットの25%向上
電波が弱かったり、干渉が多かったりする「困難な信号条件下」でも、Wi-Fi 7と比較して実効データスループットを25%向上させることを目指します。 - 遅延(レイテンシ)の25%削減
平均的な遅延だけでなく、95パーセンタイル遅延(最も遅いケースの応答性)を25%削減することを目標としています。これは、VR/ARなどの時間経過に敏感なアプリケーションにとって特に重要です。 - パケットロスの25%削減
アクセスポイント間を移動(ローミング)する際などに発生するパケットの取りこぼしを25%削減することを目指しています。これにより、移動中でも接続が途切れない安定性が実現します。
つまり、Wi-Fi 8は、どんな場所でも、どんな状況でも、「常に快適に」接続が維持されることを目的とした規格なのです。
速度の限界突破ではない?Wi-Fi 7とWi-Fi 8の決定的な違い

Wi-Fi 8はWi-Fi 7(IEEE 802.11be)の技術基盤を多く引き継いでいますが、その進化の方向性が大きく異なります。
| 特徴 | Wi-Fi 8 (802.11bn) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|---|---|
| 開発の主眼 | 超高信頼性 (UHR) | 速度と効率 | 効率と容量 |
| 理論上の最大速度 | 23 GT/s (46 Gbps) | 23 GT/s (46 Gbps) | 9.6 Gbps |
| 周波数帯 | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz | 2.4 / 5 / 6 GHz |
| 最大チャンネル幅 | 320 MHz | 320 MHz | 160 MHz |
| 最大変調方式 | 4096-QAM (※一部8192-QAMの言及あり) | 4096-QAM | 1024-QAM |
| マルチAP連携 | 対応 (Co-SR, Co-BFなど) | 非対応 | 非対応 |
| シームレスローミング | 大幅に改善 (メイク・ビフォー・ブレイクなど) | MLOは導入済みだが課題が残る | 11rベースの高速移行 |
速度はWi-Fi 7と同じだが「実効速度」が向上
Wi-Fi 8の理論上の最大物理層速度(PHY rate)は、Wi-Fi 7と同じく最大で23ギガトランスファー/秒(約46 Gbps)とされています。これは、Wi-Fi 7が既に非常に高いピーク速度を実現しているためです。
しかし、ラボ環境ではなく、実際に多くのデバイスが接続され、壁や他の電波によって干渉を受けている「実環境」での安定性(実効スループット)が、Wi-Fi 8では飛躍的に向上します。
この実効スループットの向上と低遅延化を実現する鍵が、Wi-Fi 7にはなかった「マルチAP連携」や「動的リソース制御」といった革新的な新機能なのです。
また、Wi-Fi 8は、Wi-Fi 7、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6Eといった既存の規格との後方互換性を維持するように設計されています。
【いつから?】Wi-Fi 8ルーターはいつ日本で使えるようになる?
Wi-Fi 8の標準化作業は、現在、技術開発と並行して進められています。
Wi-Fi 8(IEEE 802.11bn)の最終承認時期については、以下のスケジュールが予定されています。
- 規格のコア機能定義(Draft 1.0):近日中
- Wi-Fi Alliance認証:2028年1月予定
- IEEE 802.11ワーキンググループによる最終承認:2028年3月予定
無線通信規格は策定に数年かかり、通常、最終承認(Ratification)の前に、ドラフト仕様に基づいた製品が市場に投入され始めます。
このため、Wi-Fi 8に対応した初期デバイスやルーターは、2027年後半から2028年初頭にかけて登場し始めると予想されています。
日本での利用について
新しいWi-Fi規格の利用開始時期は、IEEEによる規格策定の進捗だけでなく、各国の電波法規制や周波数帯域の認可状況にも依存します。
たとえば、Wi-Fi 7とWi-Fi 8が共通して利用する6 GHz帯については、国や地域によって規制の状況が異なります。日本国内での認可プロセスを経て、最終的にWi-Fi 8対応製品が広く普及するのは、2028年以降となる見込みです。
「途切れない」を実現するWi-Fi 8の革新的新技術
Wi-Fi 8が追求する「超高信頼性」は、主に以下の技術によって実現されます。これらの技術は、従来のWi-Fi規格では単一のルーター(アクセスポイント/AP)が独立して動作していたのに対し、複数のAPが強調・連携して動作することが大きな特徴です。
1. マルチAP連携 (Multi AP Coordination)
アクセスポイント(AP)同士が連携し、ネットワーク全体で信号を最適化する仕組みです。
- 協調型空間再利用 (Co-SR: Coordinated Spatial Reuse)
従来のWi-Fiでは、近くのAPが送信している電波を干渉とみなし、通信を停止することがありました。Co-SRでは、複数のAPが相互に通信し、デバイスまでの距離に応じて送信電力を動的に調整します。これにより、近隣のAPと干渉することなく、同じ周波数帯域でより多くの通信が可能になり、システム全体のスループットが15%〜25%向上する可能性があります。 - 協調型ビームフォーミング (Co-BF: Coordinated Beamforming)
ビームフォーミングは特定の方向へ電波を集中させる技術ですが、Co-BFでは複数のAPが連携して電波の指向性を制御します。必要なデバイスには集中的に信号を届け、不要なエリア(干渉を引き起こす可能性のあるデバイス)には信号のヌル(無効点)を向けることで干渉を削減します。これにより、メッシュネットワーク環境下でのスループットが20%〜50%向上することが示されています。
2. 動的サブチャネル操作 (DSO: Dynamic Sub-Channel Operation)
現在のWi-Fiでは、帯域幅の割り当てが固定されがちで、リソースの無駄や混雑(輻輳)が発生していました。DSOは、接続されているデバイスの性能や要求(例:アンテナ数、処理能力)に応じて、ネットワーク帯域幅を動的かつ精密に割り当てる技術です。
例えば、最新の高性能なiPhoneやAndroidデバイスが大きなファイルをダウンロードしている場合、DSOはそのデバイスに優先的に広いサブチャネルを割り当てることで、最大80%以上のスループット向上が見込まれます。
3. 強化された長距離通信 (ELR) と分散リソースユニット (DRU)
- ELR(Enhanced Long Range)
パケット構造と符号化(コーディング)を改善することで、ルーターから離れた部屋やガレージ、屋外カメラなど電波のカバー範囲を拡大し、安定した接続を維持します。 - DRU(Distributed Resource Units)
遠隔にあるデバイスや省電力デバイス(IoT家電など)からのアップリンク信号を、より広い帯域に分散して送信出力を高める技術です。これにより、ビデオ通話やネットワークカメラなど、アップロードの信頼性が向上します。
4. シームレスローミング(Make Before Break)の改善
企業環境やメッシュネットワーク内を移動する際、デバイスはアクセスポイント間を切り替えます。従来は、古いAPから切断されてから新しいAPに接続する方式が主流でしたが、Wi-Fi 8では「メイク・ビフォー・ブレイク(Make Before Break)」と呼ばれる概念が導入されます。
これは、古い接続を切断する前に、新しいアクセスポイントへの接続を確立する(繋いでから切る)仕組みです。これにより、建物内を移動しながらビデオ会議に参加していても、通話が途切れたり、動画が固まったりする心配がなくなり、リアルタイムな通信がスムーズに継続されます。
5. 新たなMCS値(Unequal Modulation/UEQM)
電波信号がわずかに弱くなった際、通信速度が突然大きく低下し、ラグやバッファリングの原因になることがあります。
Wi-Fi 8では、この急激な速度低下を防ぐために、中間的な変調方式(MCS)の段階が追加されます。これにより、信号強度の変化に対する速度調整がより滑らかになり、移動中でも安定した接続が維持され、通信効率が5%〜30%向上する可能性があります。また、MIMO通信において、信号品質の悪いストリームに合わせて他のストリームが品質を落とす必要がなくなるUEQM(Unequal Modulation)もサポートされます。
家庭内の不安定通信はもう卒業!Wi-Fi 8は本当に必要?

「我が家には光回線が引いてあるから、Wi-Fi 8は必要ないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。しかし、Wi-Fi 8がターゲットとしているのは、光回線のピーク速度ではなく、自宅の無線環境が抱える「慢性的な不安定さ」です。
想定読者には、高解像度の動画ストリーミング、クラウドゲーミング、VR/ARを利用する方や、家族全員が同時に通信することで不安定になる家庭、スマートホームデバイス(IoT家電)を使い始めた方が含まれています。Wi-Fi 8は、まさにこれらの悩みを解消するために開発されています。
1. 家族全員が同時接続しても「遅延なし」
現代の家庭では、スマートフォン、PC、ゲーム機、スマートテレビ、ウェアラブル端末、IoT家電など、最大128台ものデバイスが同時にインターネットに接続される可能性があります。
たとえWi-Fi 7で帯域幅が広くても、同時接続によってネットワークが混雑し、遅延やパフォーマンスのバラつきが発生します。Wi-Fi 8のDSOやCo-SR技術は、この混雑をスマートに管理し、全ての接続端末(iPhone、Android、PCなど)で最適なパフォーマンスを発揮できるよう調整します。
特にFPSやクラウドゲーミングのようにPing値(遅延)に敏感なアプリケーションにおいて、Wi-Fi 8の95パーセンタイル遅延の削減は、決定的な優位性となります。
2. VR/AR、ストリーミング体験の向上
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)、そしてXR(クロスリアリティ)アプリケーションは、極めて低い遅延と一貫した高帯域幅の提供を要求します。Wi-Fi 8は、超低遅延化に加え、信頼性の高いスループットを重視することで、トレーニングシミュレーションや没入型ゲーミングにおいて、よりリッチで応答性の高い体験を実現します。
自宅のどこにいても、快適な4K/8Kストリーミングやラグのないゲームプレイが実現されることが期待されています。
3. Wi-Fiの「死角」を解消
従来のルーターでは、ルーターから離れた部屋や壁の多い環境では、信号が急激に弱まり、通信が途切れる「死角」が生まれがちでした。
Wi-Fi 8のELR(長距離通信の強化)やDRU(アップリンクの強化)技術、そしてマルチAP連携(Co-SR, Co-BF)は、複数のルーターやメッシュシステムが協調して動作することで、カバー範囲の重複による干渉を防ぎつつ、家全体で通信の安定性を向上させます。
4. 古いデバイスでも恩恵を受けられる
Wi-Fi 8対応ルーターを導入した場合、Wi-Fi 7以前の規格に接続している古いスマートフォンやPCでも、その恩恵を受けることができます。Wi-Fi 8ルーターのスマートなトラフィック管理と干渉管理のおかげで、旧規格接続時でも安定した速度、広いカバー範囲、速度低下の減少が期待できます。
VR/AR、IoT、産業を変える!Wi-Fi 8が世の中にもたらす未来

Wi-Fi 8がもたらす「超高信頼性」は、単なるエンターテイメント体験の向上に留まらず、社会インフラや産業構造そのものを変える可能性を秘めています。
1. 産業の自動化とロボット技術
工場や企業といった産業環境において、無線接続は常に信頼性が求められます。Wi-Fi 8は、自律走行車両や共同作業ロボット、ワイヤレス制御システムなど、ミッションクリティカルなシステムをサポートするために不可欠です。
Wi-Fi 8のマルチAP連携機能により、ロボットが工場内を移動しながらアクセスポイント間をシームレスにローミングしても、通信が途切れることがなくなります。また、バッテリー駆動のセンサーやIoTデバイスのエネルギー効率も向上させるため、工業用や屋外のセンサーのメンテナンスサイクルが削減されます。
2. 医療・ヘルスケア分野の進化
遠隔医療や遠隔手術といった分野では、一瞬の通信の途切れが致命的な結果につながりかねません。Wi-Fi 8の低遅延と超信頼性は、ワイヤレスによる生体情報モニターや画像診断システム、テレスコープ(遠隔手術)などの高い要求水準を満たすことができます。より安全で、予測可能性の高い医療サービスの提供が可能になります。
3. 都市インフラと公共空間
空港、スタジアム、商業施設、大学のキャンパスなど、何千ものデバイスが同時に接続される高密度な公共の場所において、Wi-Fi 8は真価を発揮します。
Co-SRやCo-BFといったAP連携技術によって、効率的に帯域を割り当て、個々のユーザー体験を損なうことなく、ARナビゲーションやライブ動画共有、緊急通信システムなどの重要なワークロードをサポートします。
4. 次世代の通信構想との関係性
Wi-Fi 8の信頼性向上への取り組みは、NTTが2030年の実現を目指す次世代ICTインフラ構想『IOWN(アイオン)』の目指す未来とも関連します。IOWN構想では、光技術を用いて圧倒的な低消費電力、超大容量化、超低遅延化(エンド・ツー・エンド遅延を200分の1まで削減)を実現することを目指しています。IOWNの目標は1秒間に1,000Tbpsを超えるデータ通信を可能にすることとされており、Wi-Fi 8が無線通信の「信頼性」を確立することで、IOWNのような革新的な有線バックボーンの性能を、末端のワイヤレスデバイス(iPhone、Android、IoT機器)まで途切れなく届ける基盤となることが期待されます。
「UHR」の恩恵と注意点!メリットとデメリットをチェック

Wi-Fi 8は非常に魅力的な規格ですが、導入を検討する上でメリットとデメリットを整理しておきましょう。
Wi-Fi 8の主なメリット
- どんな場所でも安定接続を実現
電波が弱い場所、ルーターから遠い場所、障害物が多い場所でも、実効スループットが向上します。 - 遅延(ラグ)とパケットロスが大幅に減少
VR、AR、クラウドゲーミングなど、リアルタイム性が要求されるアプリケーションの応答性が劇的に改善します。 - ローミング(移動)時の通信が途切れない
オフィスや広い家でアクセスポイント間を移動しても、シームレスな接続(メイク・ビフォー・ブレイク)が実現し、ビデオ通話などが安定します。 - 高密度環境に強い
多数のデバイスが接続される家庭やオフィス、公共空間で、AP同士が協調して干渉を防ぐため、通信の混雑が回避されます。 - 省電力デバイス(IoT)に優しい
高度な電源管理機能やDRU、ELR技術により、バッテリー駆動のスマートホームデバイスの動作時間延長につながります。
Wi-Fi 8の注意点(デメリット)
- 現時点ではまだ標準化の途中
最終的な規格承認は2028年3月と予定されており、現時点では仕様が変更される可能性があります。早期製品(ドラフト仕様ベース)は登場する可能性がありますが、標準化された製品が出回るまで待つ必要があります。 - 初期コストが発生する可能性
Wi-Fi 8の恩恵を最大限に受けるには、Wi-Fi 8に対応したルーター(アクセスポイント)と、対応するスマートフォンやPC(クライアントデバイス)が必要になります。新しいルーターやデバイス(iPhoneやAndroidの次世代機など)を導入するための初期費用が発生するでしょう。
次世代のWi-Fiは「繋がり続ける安心」を約束してくれる
Wi-Fi 8は、長年私たちを悩ませてきた「無線通信の不安定さ」という根本的な課題に正面から向き合った規格です。
かつてのWi-Fiが、道路の「最高速度」を競い合っていたとするならば、Wi-Fi 8は、「どれだけ渋滞しても、遠くまで行っても、快適な速度で走り続けられる道路」を作ることに成功しました。
私たちがWi-Fiに期待するのは、特定の瞬間に出る「驚異的な速度」よりも、むしろ「使いたいときに、確実に、途切れることなく使える」という安心感です。
Wi-Fi 8の実現により、高解像度の動画ストリーミングが途切れる不安、VR/ARで酔ってしまうほどの遅延の不安は解消され、家中のどこにいても、まるで有線接続のように安定した「永遠なる接続」が実現する日も遠くありません。
2028年の標準化完了、そしてその後に登場するWi-Fi 8ルーターやデバイスの動向に、ぜひご期待ください。
みんなのらくらくマガジン 編集長 / 悟知(Satoshi)
SEOとAIの専門家。ガジェット/ゲーム/都市伝説好き。元バンドマン(作詞作曲)。SEO会社やEC運用の経験を活かし、「らくらく」をテーマに執筆。社内AI運用管理も担当。